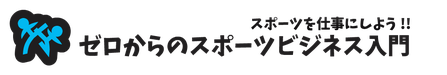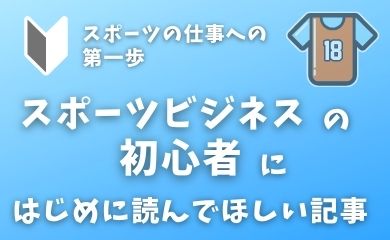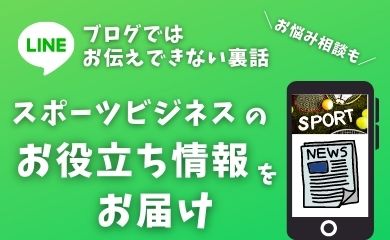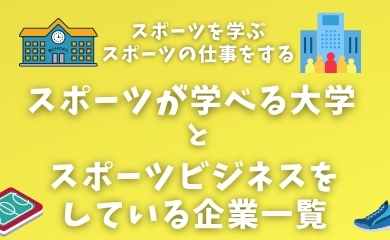全国のどこに、どんな総合型スポーツクラブがあるのかな!? というのを知りたい方のために、「全国の総合型スポーツクラブ一覧」を作ってみました!!
あなたの住んでいる地域や地元にも、実は総合型スポーツクラブが活動していたりするかも!?
ここに載っている総合型スポーツクラブ以外にも、全国には様々なクラブが存在しています。詳細は、各都道府県のスポーツ協会などのホームページでご確認ください。
/
スポーツビジネスの「お悩み相談」や学びをお届けする「オンラインマガジン」をLINEでやってます😆📣
\
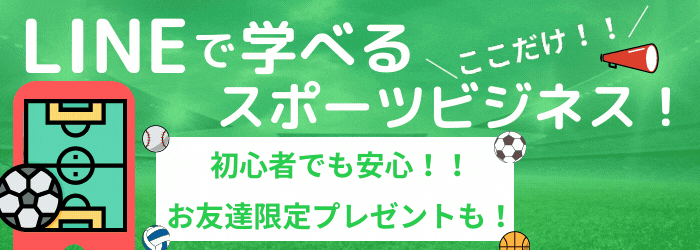
| 都道府県 | 市区町村 | クラブ名 |
|---|---|---|
| 北海道 | 和寒町 | わっさむフレンドパーク |
| 北海道 | 留萌市 | るもいスポーツクラブ「このゆびとまれ」 |
| 北海道 | 羅臼町 | NPO法人羅臼スポーツクラブらいず |
| 北海道 | 余市町 | 特定非営利活動法人よいスポ |
| 北海道 | 夕張市 | ユるっとゆうばりスポーツクラブ |
| 北海道 | 夕張市 | 特定非営利活動法人あ・リーさだ |
| 北海道 | 由仁町 | 由仁スポーツクラブ |
| 北海道 | 網走市 | 特定非営利活動法人あばしりスポーツクラブ |
| 北海道 | 名寄市 | 一般社団法人風連スポーツクラブ |
| 北海道 | 幕別町 | 特定非営利活動法人幕別札内スポーツクラブ |
| 北海道 | 幕別町 | 一般社団法人十勝総合型スポーツクラブ フーニ |
| 北海道 | 北斗市 | 特定非営利活動法人北斗スポーツクラブ |
| 北海道 | 北広島市 | 特定非営利活動法人法人 きたひろちょいスポ倶楽部 |
| 北海道 | 北広島市 | 一般社団法人わくわくピース総合型クラブ |
| 北海道 | 北海道 | みなみふらのSHCクラブ ゆっく |
| 北海道 | 標津町 | NPO法人標津スポーツクラブすぽっと |
| 北海道 | 美幌町 | びほろスポーツクラブBeet |
| 北海道 | 美深町 | 特定非営利法人びふかスポーツクラブ |
| 北海道 | 美唄市 | 美唄どんまいスポーツクラブ |
| 北海道 | 函館市 | 一般社団法人ミスポはこだて |
| 北海道 | 函館市 | 総合型潮スポーツクラブ |
| 北海道 | 函館市 | 総合型地域スポーツクラブBayWalkCommunityはこだて |
| 北海道 | 苫小牧市 | 一般社団法人総合型地域スポーツクラブとまこまい・あそび塾 |
| 北海道 | 当麻町 | 特定非営利活動法人とうまスポーツクラブ |
| 北海道 | 当別町 | 特定非営利活動法人 ふれ・スポ・とうべつ |
| 北海道 | 登別市 | 特定非営利活動法人おにスポ |
| 北海道 | 弟子屈町 | 摩周ふれあいスポーツクラブ |
| 北海道 | 中標津町 | NPOなかしべつスポーツアカデミー |
| 北海道 | 中川町 | 中川町総合型地域スポーツクラブ「なかがわスポーツくらぶ」 |
| 北海道 | 帯広市 | 清柳スポーツクラブ |
| 北海道 | 帯広市 | 特定非営利活動法人緑ヶ丘スポーツクラブ |
| 北海道 | 帯広市 | おびひろの森スポーツクラブ「はつらつ」 |
| 北海道 | 帯広市 | 帯広市教育委員会生涯学習部スポーツ室スポーツ課 |
| 北海道 | 壮瞥町 | NPO法人そうべつ地遊スポーツクラブ |
| 北海道 | 石狩市 | 石狩市総合型地域スポーツクラブ アクト |
| 北海道 | 清水町 | 特定非営利活動法人清水町体育協会 |
| 北海道 | 仁木町 | 銀山地区総合型地域スポーツクラブ |
| 北海道 | 新十津川町 | 特定非営利活動法人新十津川スポーツ協会 新十津川スポーツクラブ |
| 北海道 | 新篠津村 | 遊ゆうクラブ |
| 北海道 | 沼田町 | 一般社団法人N-link. |
| 北海道 | 小樽市 | 後志Ruumu.SC総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会 |
| 北海道 | 小樽市 | FANスポーツクラブ |
| 北海道 | 初山別村 | 初山別総合型クラブ「楽すぽクラブ」 |
| 北海道 | 室蘭市 | 室蘭市中央地区スポーツクラブ |
| 北海道 | 鹿部町 | 鹿部カールスクラブ |
| 北海道 | 枝幸町 | 特定非営利活動法人枝幸三笠山スポーツクラブ(エムスク) |
| 北海道 | 士別市 | 士別中央スポーツクラブ |
| 北海道 | 士別市 | 多寄スポーツクラブ |
| 北海道 | 三笠市 | みかさスポーツクラブぽっけ |
| 北海道 | 札幌市 | 特定非営利活動法人札幌オールカマースポーツ倶楽部 |
| 北海道 | 札幌市 | 特定非営利活動法人真駒内スポーツコミュニティークラブ |
| 北海道 | 札幌市 | 特定非営利活動法人AGGREスポーツクラブ |
| 北海道 | 札幌市 | 一般社団法人コンサドーレ北海道スポーツクラブ |
| 北海道 | 札幌市 | Hokkaido Adaptive Sports |
| 北海道 | 札幌市 | さっぽろ運動あそびクラブ |
| 北海道 | 根室市 | ねむろコミュニティスポーツくらぶ |
| 北海道 | 今金町 | 総合型地域スポーツクラブいまかね |
| 北海道 | 江別市 | 北翔大学スポルクラブ |
| 北海道 | 恵庭市 | 北海道ハイテクACアカデミー |
| 北海道 | 釧路町 | 総合型クラブ 釧路スポーツ&カルチャークラブ |
| 北海道 | 釧路市 | 特定非営利活動法人桜が丘ひぶなクラブ |
| 北海道 | 釧路市 | グルスの杜あかん スポーツくらぶ |
| 北海道 | 釧路市 | 大楽毛げんきスポーツクラブ |
| 北海道 | 釧路市 | とらいあんぐる946 |
| 北海道 | 岩見沢市 | 地域スポーツクラブSLDI |
| 北海道 | 音更町 | 一般社団法人おん・おーる |
| 北海道 | 安平町 | 特定非営利活動法人アビースポーツクラブ |
| 北海道 | 旭川市 | 高台チャレンジクラブ |
| 北海道 | 旭川市 | 一般社団法人旭川東豊スポーツクラブ |
| 北海道 | 旭川市 | 一般社団法人旭川緑が丘スポーツクラブ |
| 北海道 | むかわ町 | 特定非営利活動法人むーブ |
| 北海道 | せたな町 | 総合型スポーツクラブせたな |
| 青森県 | つがる市 | いながきスポーツクラブ |
| 青森県 | つがる市 | 車力楽笑スポーツクラブ |
| 青森県 | むつ市 | むつアスリートクラブ |
| 青森県 | 階上町 | 一般社団法人ライズはしかみ |
| 青森県 | 外ヶ浜町 | 東津軽郡スポーツクラブ |
| 青森県 | 五戸町 | 五戸町スポーツクラブ |
| 青森県 | 五所川原市 | 五所川原総合スポーツクラブ |
| 青森県 | 弘前市 | NPO法人スポネット弘前 |
| 青森県 | 弘前市 | NPO法人リベロ津軽スポーツクラブ |
| 青森県 | 黒石市 | くろいしアスリートアンドエンジョイクラブ |
| 青森県 | 今別町 | 今別町地域総合型クラブ「WAND」 |
| 青森県 | 三戸町 | 一般社団法人さんのへスポーツクラブEnjoy |
| 青森県 | 三種町 | 琴丘地域スポーツクラブ連盟 |
| 青森県 | 三沢市 | スポーツクラブみさわ |
| 青森県 | 十和田市 | 総合型スポーツクラブRED HORSE |
| 青森県 | 新郷村 | 三ツ岳スポーツクラブ |
| 青森県 | 深浦町 | 深浦町総合型地域スポーツクラブ「Joy Spo! ふかうら」 |
| 青森県 | 青森市 | 青森総合スポーツクラブ |
| 青森県 | 青森市 | Willスポーツクラブ |
| 青森県 | 青森市 | CLUB Salute |
| 青森県 | 大間町 | 大間町総合型地域スポーツクラブ |
| 青森県 | 大鰐町 | 一般社団法人Roots大鰐 |
| 青森県 | 鶴田町 | 鶴田町放課後子どもプラン・子どもスポーツクラブ |
| 青森県 | 田子町 | スポネットたっこ |
| 青森県 | 東北町 | 東北町旭町地区総合型地域スポーツクラ |
| 青森県 | 藤崎町 | ふじさきいきいきスポーツクラブ |
| 青森県 | 南部町 | 総合型クラブ ななっち |
| 青森県 | 八戸市 | ヴァンラーレ八戸スポーツクラブ |
| 青森県 | 八戸市 | ウィンズスポーツクラブ |
| 青森県 | 板柳町 | りんごの里スポーツクラブ |
| 青森県 | 平川市 | ひらかわスポーツクラブ |
| 青森県 | 平内町 | 平内ふれあいスポーツクラブ |
| 青森県 | 蓬田村 | よもっと元気スポーツクラブ |
| 青森県 | 六ケ所村 | ひばりさわやかスポーツクラブ |
| 青森県 | 六戸町 | 六戸町B&Gクラブ |
| 青森県 | 鰺ヶ沢町 | 鰺ヶ沢町スポーツクラブ |
| 青森県 | 東通村 | 東通村総合型地域スポーツクラブ |
| 青森県 | 八戸市 | 一般社団法人総合型地域スポーツHachinohe Club |
| 秋田県 | にかほ市 | 特定非営利活動法人BSスポーツクラブにかほ |
| 秋田県 | 井川町 | いかわスポーツクラブ |
| 秋田県 | 羽後町 | 羽後町スポーツクラブ |
| 秋田県 | 横手市 | よこてスポーツクラブ |
| 秋田県 | 横手市 | 特定非営利活動法人大森スポーツクラブさくら |
| 秋田県 | 潟上市 | 昭和スポーツクラブ |
| 秋田県 | 潟上市 | 潟上南スポーツクラブ |
| 秋田県 | 潟上市 | 潟上天王スポーツクラブ |
| 秋田県 | 五城目町 | 五城目総合型スポーツクラブ「ゴスパル」 |
| 秋田県 | 三種町 | 八竜地域スポーツクラブ |
| 秋田県 | 三種町 | 山本地域スポーツクラブ |
| 秋田県 | 鹿角市 | NPO鹿角くらすた |
| 秋田県 | 鹿角市 | 総合型地域スポーツクラブ鹿角ウインプルスポーツクラブ |
| 秋田県 | 鹿角市 | 十和田スポーツクラブ |
| 秋田県 | 秋田市 | グリーン健康倶楽部 |
| 秋田県 | 秋田市 | 特定非営利活動法人スポーツクラブあきた |
| 秋田県 | 秋田市 | グリーン巽会 |
| 秋田県 | 秋田市 | NPO法人総合型地域スポーツクラブスポルティフ秋田 |
| 秋田県 | 秋田市 | 秋田ノーザンブレッツラグビーフットボールクラブ |
| 秋田県 | 秋田市 | 下浜スポーツクラブSUN-Q |
| 秋田県 | 秋田市 | 弥生スポーツクラブ |
| 秋田県 | 秋田市 | 千秋スポーツクラブ |
| 秋田県 | 秋田市 | 修武館土崎スポーツクラブ |
| 秋田県 | 秋田市 | スポーツクラブK-fit |
| 秋田県 | 秋田市 | スポーツクラブFan |
| 秋田県 | 小坂町 | 小坂町スポーツクラブ |
| 秋田県 | 上小阿仁村 | かみこあに総合型クラブスマイル |
| 秋田県 | 仙北市 | たざわ湖スポーツクラブ |
| 秋田県 | 仙北市 | 角館総合型地域スポーツクラブ |
| 秋田県 | 仙北市 | 特定非営利活動法人きたうらアクアスポーツクラブ |
| 秋田県 | 仙北市 | 檜木内てくてく倶楽部 |
| 秋田県 | 仙北市 | 神代スポーツクラブ |
| 秋田県 | 大潟村 | 特定非営利活動法人スポ-レおおがた |
| 秋田県 | 大館市 | 大館総合スポーツクラブブレイジングトルシーダ大館 |
| 秋田県 | 大館市 | スポーツクラブひない |
| 秋田県 | 大館市 | たしろスポーツクラブ |
| 秋田県 | 大仙市 | 大曲スポーツクラブ |
| 秋田県 | 大仙市 | 内小友スポーツクラブ |
| 秋田県 | 大仙市 | おおたスポーツクラブ |
| 秋田県 | 大仙市 | 花館グリーンウインズスポーツクラブ |
| 秋田県 | 大仙市 | 中仙スポーツクラブ |
| 秋田県 | 大仙市 | 大仙協和スポーツクラブ |
| 秋田県 | 大仙市 | 西仙北スポーツクラブ |
| 秋田県 | 大仙市 | 特定非営利活動法人大仙スポーツクラブ |
| 秋田県 | 大仙市 | せんぼくスポーツクラブ |
| 秋田県 | 男鹿市 | 男鹿市総合型地域スポーツクラブ |
| 秋田県 | 男鹿市 | 総合型地域スポーツクラブアスレチッククラブグロース男鹿 |
| 秋田県 | 東成瀬村 | 仙人の郷スポーツクラブ |
| 秋田県 | 湯沢市 | みなせスポーツ・文化クラブ「楽日人」 |
| 秋田県 | 湯沢市 | NPO法人こまちハート・オブ・ゴールド |
| 秋田県 | 湯沢市 | チャレンジスポーツクラブいなかわ |
| 秋田県 | 湯沢市 | 湯沢ゆうゆう総合型地域スポーツクラブ |
| 秋田県 | 湯沢市 | 特定非営利活動法人ゆざわサンマリッツスポーツクラブ |
| 秋田県 | 藤里町 | ふじさとスポーツクラブ |
| 秋田県 | 能代市 | 常磐の里スポーツクラブ |
| 秋田県 | 能代市 | 特定非営利活動法人スポカルきみまち |
| 秋田県 | 能代市 | 東能代地区にこにこスポーツクラブ |
| 秋田県 | 能代市 | スポーツクラブのしろ |
| 秋田県 | 八峰町 | 八森はたはたスポーツクラブ |
| 秋田県 | 八郎潟町 | 八郎潟町総合スポーツクラブ |
| 秋田県 | 美郷町 | 美郷町総合型スポーツクラブ |
| 秋田県 | 北秋田市 | あいあいクラブたかのす |
| 秋田県 | 北秋田市 | 小猿部スポーツクラブ |
| 秋田県 | 北秋田市 | 森吉クマゲラスポーツクラブ |
| 秋田県 | 北秋田市 | 合川スポーツクラブ |
| 秋田県 | 北秋田市 | 阿仁スポーツクラブ |
| 秋田県 | 由利本荘市 | 尾崎スポーツクラブ |
| 秋田県 | 由利本荘市 | SPORTS・POPORO |
| 秋田県 | 由利本荘市 | 石脇スポーツクラブ |
| 岩手県 | 一関市 | 藤沢町体育協会 |
| 岩手県 | 一関市 | NPO法人ファンスポルト一関 |
| 岩手県 | 一関市 | NPO法人グッジョブクラブ |
| 岩手県 | 一戸町 | 奥中山高原クラブ |
| 岩手県 | 一戸町 | いちのへサンビレッヂクラブ |
| 岩手県 | 遠野市 | とおのスポーツクラブ |
| 岩手県 | 遠野市 | 綾織スポーツクラブ |
| 岩手県 | 遠野市 | 小友スポーツクラブ |
| 岩手県 | 遠野市 | 早池峰スポーツクラブ |
| 岩手県 | 遠野市 | 松崎スポーツクラブ |
| 岩手県 | 遠野市 | 小烏瀬地域スポーツクラブ |
| 岩手県 | 遠野市 | 青笹スポーツクラブ |
| 岩手県 | 遠野市 | 上郷センニンスポーツクラブ |
| 岩手県 | 遠野市 | 宮守町総合型地域スポーツクラブ |
| 岩手県 | 遠野市 | NPO法人オヴェンセ |
| 岩手県 | 遠野市 | 遠野薬師総合型スポーツクラブ |
| 岩手県 | 奥州市 | 総合型真城体育協会 |
| 岩手県 | 奥州市 | 総合型佐倉河スポーツクラブ |
| 岩手県 | 奥州市 | みずさわZスポーツクラブ |
| 岩手県 | 奥州市 | NPO法人前沢いきいきスポーツクラブ |
| 岩手県 | 奥州市 | NPO法人シチズンスポーツ奥州 |
| 岩手県 | 花巻市 | (一財)花巻市体育協会 |
| 岩手県 | 花巻市 | 特例認定NPO法人Sumはなまき |
| 岩手県 | 花巻市 | 花巻総合型地域スポーツクラブNorthern Rise |
| 岩手県 | 葛巻町 | NPO法人葛巻町体育協会スポーツクラブ |
| 岩手県 | 釜石市 | 釜石シーウェイブスRFC |
| 岩手県 | 釜石市 | 唐丹地区すぽこんクラブ |
| 岩手県 | 岩手町 | 一般財団法人岩手町体育協会スポーツクラブ |
| 岩手県 | 岩泉町 | NPO法人岩泉地域活動推進センター 岩泉スポーツクラブ |
| 岩手県 | 久慈市 | 久慈フィ-バスポーツクラブ |
| 岩手県 | 宮古市 | シーアリーナスポーツクラブ |
| 岩手県 | 宮古市 | NPO法人エムジョイ |
| 岩手県 | 金ヶ崎町 | 森山スポーツ倶楽部 |
| 岩手県 | 金ヶ崎町 | NPO法人金ヶ崎スポーツクラブ |
| 岩手県 | 紫波町 | 紫波ウィング |
| 岩手県 | 雫石町 | 御所地区体育会 |
| 岩手県 | 雫石町 | NPO法人雫石なつめ倶楽部 |
| 岩手県 | 住田町 | カムイくらぶ |
| 岩手県 | 盛岡市 | NPO法人まつぞのスポーツクラブ |
| 岩手県 | 盛岡市 | コミスポクラブ東厨川 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 見前地区体育振興会 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 一般社団法人Bondsスポーツクラブ |
| 岩手県 | 盛岡市 | NPO法人いーはとーぶスポーツクラブ |
| 岩手県 | 盛岡市 | NPO法人3D SPORTS |
| 岩手県 | 盛岡市 | NPO法人たますぽ |
| 岩手県 | 大船渡市 | SUN陸リアススポーツクラブ |
| 岩手県 | 大槌町 | 吉里吉里スポーツクラブ |
| 岩手県 | 滝沢市 | 公益財団法人滝沢市体育協会チャグチャグスポーツクラブ |
| 岩手県 | 田野畑村 | 田野畑村スポーツクラブ |
| 岩手県 | 二戸市 | カシオペア氷上スポーツクラブ |
| 岩手県 | 二戸市 | 浄法寺スポーツクラブ |
| 岩手県 | 普代村 | はまゆりスポーツクラブ |
| 岩手県 | 北上市 | NPO法人北上アスレチック&ラグビー倶楽部 |
| 岩手県 | 北上市 | サークルS&Cいいとよ |
| 岩手県 | 北上市 | NPO法人フォルダ |
| 岩手県 | 北上市 | 和賀総合型スポーツクラブOne's |
| 岩手県 | 矢巾町 | 楽々クラブ矢巾 |
| 岩手県 | 洋野町 | 洋野町総合型地域スポーツクラブ |
| 岩手県 | 陸前高田市 | NPO法人総合型りくぜんたかた |
| 岩手県 | 陸前高田市 | 一般社団法人三陸・気仙総合型スポーツクラブ |
| 山形県 | 河北町 | 河北町スポーツクラブ |
| 山形県 | 寒河江市 | 寒河江市総合スポーツクラブ |
| 山形県 | 金山町 | 金山健康ふれあいスポーツクラブ |
| 山形県 | 戸沢村 | NPO法人とざわスポーツクラブ |
| 山形県 | 最上町 | もがみ西公園スポーツクラブ |
| 山形県 | 鮭川村 | さけがわ友遊C'Love |
| 山形県 | 三川町 | みかわスポーツクラブ |
| 山形県 | 山形市 | NPO法人生涯スポーツ振興会(アプルス) |
| 山形県 | 山形市 | ほなみふれあいスポーツクラブ |
| 山形県 | 山形市 | 山形市体育協会スポーツクラブ |
| 山形県 | 山形市 | 一般財団法人ベニバナ夢未来クラブ |
| 山形県 | 山形市 | NPO法人山形TFC |
| 山形県 | 山辺町 | 山辺の里スポーツクラブ |
| 山形県 | 酒田市 | 特定非営利活動法人希望ヶ丘体育文化振興会 |
| 山形県 | 酒田市 | 鳥海ふれあいスポーツクラブ |
| 山形県 | 酒田市 | 酒田市スポーツクラブ |
| 山形県 | 酒田市 | やわたY-Yクラブ |
| 山形県 | 酒田市 | 松山総合型地域スポーツクラブ「みなスポ 松山」 |
| 山形県 | 酒田市 | NPO法人元気王国 |
| 山形県 | 酒田市 | ひらた目ん玉スポーツクラブ |
| 山形県 | 酒田市 | きらり川南スポーツクラブ |
| 山形県 | 舟形町 | 舟形町総合型スポーツクラブB&G |
| 山形県 | 小国町 | 特定非営利活動法人おぐにスポーツクラブYui(結) |
| 山形県 | 庄内町 | 庄内町総合型スポーツクラブ「コメッち*わくわくクラブ゙」 |
| 山形県 | 上山市 | NPO法人かみのやま総合型地域スポーツクラブ |
| 山形県 | 新庄市 | かむてんスポーツクラブ |
| 山形県 | 川西町 | マイマイスポーツクラブ |
| 山形県 | 川西町 | スポーツかわにし |
| 山形県 | 村山市 | 村山アスレチッククラブ |
| 山形県 | 村山市 | 徳内ふれあいスポーツクラブ |
| 山形県 | 大江町 | 大江スポーツクラブ 0-STEP |
| 山形県 | 大石田町 | 大石田スポーツクラブ |
| 山形県 | 大蔵村 | NPO法人Oh!蔵SPORT |
| 山形県 | 中山町 | NPO法人中山総合スポーツクラブ |
| 山形県 | 朝日町 | 朝日ふれあいスポーツクラブ |
| 山形県 | 長井市 | 西根ときめきスポーツクラブ |
| 山形県 | 長井市 | 長井花のまちスポーツクラブ |
| 山形県 | 鶴岡市 | 鶴岡市民健康スポーツクラブ |
| 山形県 | 鶴岡市 | 稲穂ファミリースポーツクラブ |
| 山形県 | 鶴岡市 | NPO法人たかだてスポーツクラブ |
| 山形県 | 鶴岡市 | あつみスポーツクラブ ネクサス |
| 山形県 | 鶴岡市 | デポルターレ豊浦 |
| 山形県 | 鶴岡市 | ふじしまスポーツクラブ |
| 山形県 | 鶴岡市 | くしびきスポーツクラブ |
| 山形県 | 鶴岡市 | あさひスポーツクラブ |
| 山形県 | 鶴岡市 | はぐろスポーツクラブ |
| 山形県 | 天童市 | あかねエンジョイクラブ |
| 山形県 | 天童市 | 公益財団法人山形県スポーツ振興21世紀協会 |
| 山形県 | 東根市 | マイ・スポーツひがしね |
| 山形県 | 南陽市 | 特定非営利活動法人沖郷スポーツクラブ |
| 山形県 | 南陽市 | 南陽市四道会スポーツクラブ |
| 山形県 | 飯豊町 | 特定非営利活動法人いいでスポーツクラブ キララ |
| 山形県 | 尾花沢市 | NPO法人尾花沢総合スポーツクラブ |
| 山形県 | 米沢市 | アルカディアスポーツクラブ |
| 山形県 | 米沢市 | スポーツクラブ OMONO |
| 山形県 | 米沢市 | 特定非営利活動法人スポーツクラブ米沢 |
| 山形県 | 遊佐町 | 遊佐町総合型スポーツ文化クラブ「遊’s」 |
| 宮城県 | 塩釜市 | 一般社団法人塩竈フットボールクラブ |
| 宮城県 | 加美町 | NPO法人ジョイナス |
| 宮城県 | 角田市 | NPO法人スポーツコミュニケーションかくだ(スポコム・かくだ) |
| 宮城県 | 丸森町 | スポーツクラブ大内 |
| 宮城県 | 岩沼市 | レッツいわぬまスポーツネット |
| 宮城県 | 気仙沼市 | NPO法人なんでもエンジョイ面瀬クラブ |
| 宮城県 | 栗原市 | しわひめスポーツクラブ |
| 宮城県 | 栗原市 | わかやなぎスポーツクラブ |
| 宮城県 | 七ヶ浜町 | NPO法人アクアゆめクラブ |
| 宮城県 | 松島町 | NPO法人マリソル松島スポーツクラブ |
| 宮城県 | 石巻市 | いしのまき総合スポーツクラブ |
| 宮城県 | 仙台市宮城野区 | NPO法人レオクラブジャパン |
| 宮城県 | 仙台市青葉区 | NPO法人Place Of Play仙台 |
| 宮城県 | 仙台市青葉区 | KHKスポーツクラブASPA |
| 宮城県 | 仙台市青葉区 | ゼファスポーツクラブ |
| 宮城県 | 仙台市泉区 | NPO法人泉パークタウンSPO&COMクラブ “DUO” |
| 宮城県 | 仙台市泉区 | 向陽台総合型地域スポーツ・文化クラブ(向陽台倶楽部) |
| 宮城県 | 仙台市泉区 | 南光台東エンジョイ倶楽部 |
| 宮城県 | 仙台市太白区 | 総合型地域Enableスポーツクラブ |
| 宮城県 | 多賀城市 | NPO法人多賀城市民スポーツクラブ |
| 宮城県 | 美里町 | スポーツクラブWAY" |
| 宮城県 | 富谷市 | とみやスポーツクラブ |
| 宮城県 | 名取市 | 尚絅学院大学総合型地域スポーツクラブ絆・KIZUNA |
| 宮城県 | 名取市 | 一般社団法人ボディジャンプ |
| 宮城県 | 利府町 | NPO法人りふスポーツクラブ‘スポメイトりふ’ |
| 福島県 | いわき市 | NPO法人いわきクラブ |
| 福島県 | いわき市 | 泉クラブ |
| 福島県 | いわき市 | いわきフォーウインズスポーツファミリークラブ |
| 福島県 | いわき市 | NPO法人いわきFスポーツクラブ |
| 福島県 | いわき市 | NPO法人いわき・あいスポねっと |
| 福島県 | 会津坂下町 | NPO法人スポーツクラブバンビィ |
| 福島県 | 会津若松市 | 謹教スポーツクラブ |
| 福島県 | 会津若松市 | きたあいづスポーツクラブ |
| 福島県 | 会津美里町 | NPO法人会津美里クラブ衆 |
| 福島県 | 葛尾村 | かつらおスポーツクラブ |
| 福島県 | 喜多方市 | NPO法人ひめさゆりくらぶ |
| 福島県 | 喜多方市 | やまとスポーツクラブ |
| 福島県 | 鏡石町 | NPO法人かがみいしスポーツクラブ |
| 福島県 | 玉川村 | NPO法人たまかわ元気スポーツクラブ |
| 福島県 | 桑折町 | マルベリーこおり |
| 福島県 | 郡山市 | 緑ヶ丘スポーツクラブ |
| 福島県 | 郡山市 | 小原田スポーツクラブ |
| 福島県 | 郡山市 | Vivakidsスポーツクラブ |
| 福島県 | 古殿町 | FULLSPO |
| 福島県 | 広野町 | NPO法人広野みかんクラブ |
| 福島県 | 鮫川村 | NPO法人さめがわスポーツクラブ |
| 福島県 | 小野町 | こまちスポーツクラブ |
| 福島県 | 新地町 | チャレンジしんち |
| 福島県 | 西会津町 | 西会津スポーツクラブ |
| 福島県 | 西郷村 | NPO法人西の郷スポーツクラブ |
| 福島県 | 川内村 | かわうちKOMERAクラブ |
| 福島県 | 川俣町 | NPO法人かわまたスポーツクラブ |
| 福島県 | 双葉町 | NPO法人双葉ふれあいクラブ |
| 福島県 | 相馬市 | NPO法人そうま中央スポーツクラブ |
| 福島県 | 大熊町 | NPO法人おおくまスポーツクラブ |
| 福島県 | 棚倉市 | 棚倉スポーツクラブ |
| 福島県 | 楢葉町 | (一社)楢葉町スポーツ協会 |
| 福島県 | 南相馬市 | 太田大甕スポーツクラブ |
| 福島県 | 南相馬市 | NPO法人はらまちクラブ |
| 福島県 | 南相馬市 | 浮舟うきうきクラブ |
| 福島県 | 南相馬市 | NPO法人かしま元気クラブ |
| 福島県 | 二本松市 | (一社)いわしろふれあいスポーツクラブ |
| 福島県 | 二本松市 | 東和さわやかスポーツクラブ |
| 福島県 | 二本松市 | あだちスポーツクラブ |
| 福島県 | 二本松市 | (一社)にほんまつ城山クラブ |
| 福島県 | 二本松市 | 岳クラブ |
| 福島県 | 白河市 | スポーツクラブ「仲間」 |
| 福島県 | 白河市 | 大沼ふれあいスポーツクラブ |
| 福島県 | 白河市 | 関山スポーツクラブ |
| 福島県 | 白河市 | あけどスポーツクラブ |
| 福島県 | 白河市 | 21’スポーツクラブinしらかわ |
| 福島県 | 白河市 | NPO法人チーム青い空 |
| 福島県 | 塙町 | NPO法人はなわスポーツクラブ |
| 福島県 | 飯舘村 | いいたてスポーツクラブ |
| 福島県 | 富岡町 | (公社)富岡町さくら文化・スポーツ振興公社 |
| 福島県 | 福島市 | NPO法人福島スポーツネット |
| 福島県 | 平田村 | ひらたスポーツクラブ |
| 福島県 | 本宮市 | もとみやスポーツネットワーク |
| 福島県 | 矢吹町 | 矢吹スポーツクラブ |
| 福島県 | 柳津町 | NPO法人赤べこトータルスポーツ |
| 新潟県 | 阿賀野市 | NPO法人阿賀野市総合型クラブ |
| 新潟県 | 燕市 | 燕市総合型スポーツクラブ |
| 新潟県 | 魚沼市 | NPO法人エンジョイスポーツクラブ魚沼 |
| 新潟県 | 見附市 | NPO法人見附市総合型地域スポーツクラブ |
| 新潟県 | 五泉市 | 一般社団法人五泉市スポーツ協会総合型クラブ ヴィガ |
| 新潟県 | 三条市 | 学区総合型クラブ ますがたクラブ |
| 新潟県 | 三条市 | 三条市総合型地域スポーツクラブりんぐる |
| 新潟県 | 十日町市 | NPO法人ネージュスポーツクラブ |
| 新潟県 | 小千谷市 | こいこいスポーツクラブおぢや |
| 新潟県 | 上越市 | NPO法人ユートピアくびきスポーツクラブ |
| 新潟県 | 上越市 | NPO法人さんわスポーツクラブ |
| 新潟県 | 上越市 | かきざきスポーツクラブ |
| 新潟県 | 上越市 | NPO法人おおがたスポーツクラブ |
| 新潟県 | 新潟市 | NPO法人総合型地域スポーツクラブ ハピスカとよさか |
| 新潟県 | 新発田市 | 認定NPO法人新発田市総合型地域スポーツクラブ |
| 新潟県 | 聖籠町 | NPO法人スポネットせいろう |
| 新潟県 | 村上市 | NPO法人希楽々 |
| 新潟県 | 村上市 | NPO法人総合型スポーツクラブウェルネスむらかみ |
| 新潟県 | 村上市 | NPO法人総合型地域スポーツクラブ愛ランドあさひ |
| 新潟県 | 村上市 | NPO法人サンスマイルあらかわ |
| 新潟県 | 村上市 | NPO法人さんぽくスポーツ協会 |
| 新潟県 | 胎内市 | NPO法人スポーツクラブたいない |
| 新潟県 | 長岡市 | 長岡蒼柴スポーツクラブ |
| 新潟県 | 長岡市 | 一般社団法人長岡かわぐちスポーツクラブ |
| 新潟県 | 長岡市 | 総合型クラブY-GETS |
| 新潟県 | 長岡市 | 寺泊総合型スポーツクラブ てらスポ! |
| 新潟県 | 長岡市 | 一般社団法人キラスポみしま |
| 新潟県 | 長岡市 | NPO法人長岡ジュニアユースフットボールクラブ |
| 新潟県 | 津南町 | NPO法人Tap |
| 新潟県 | 湯沢町 | NPO法人ユースポ! |
| 新潟県 | 南魚沼市 | 南魚スポーツパラダイス |
| 新潟県 | 柏崎市 | NPO法人チャレンジ夢クラブ |
| 新潟県 | 妙高市 | NPO法人スポーツクラブあらい |
| 新潟県 | 妙高市 | 妙高高原スポーツクラブ |
| 新潟県 | 妙高市 | NPO法人ふるさとづくり妙高 |
| 富山県 | 滑川市 | なめりCANクラブ |
| 富山県 | 魚津市 | 天神文化スポーツクラブ |
| 富山県 | 魚津市 | うおづスポラ |
| 富山県 | 高岡市 | AQUOS万葉スポーツクラブ |
| 富山県 | 高岡市 | NPO法人 遊・Uクラブ |
| 富山県 | 黒部市 | (公財)黒部市体育協会KUROBEスポーツファミリー |
| 富山県 | 黒部市 | NPO法人 KUスポーツクラブWill |
| 富山県 | 射水市 | NPO法人 新湊カモンスポーツクラブ |
| 富山県 | 射水市 | NPO法人 こすぎ総合スポーツクラブ きらり |
| 富山県 | 射水市 | NPO法人 だいもんスポーツクラブ |
| 富山県 | 射水市 | NPO法人 しもむらスポーツクラブ まいけ |
| 富山県 | 射水市 | NPO法人 おおしまスポーツクラブ |
| 富山県 | 舟橋村 | (一社)常願寺川公園スポーツクラブ |
| 富山県 | 小矢部市 | NPO法人 おやべスポーツクラブ |
| 富山県 | 上市町 | 上市町総合スポーツクラブ さんさん |
| 富山県 | 朝日町 | ひすいスポーツクラブ |
| 富山県 | 砺波市 | NPO法人 SEIBUスポーツクラブ |
| 富山県 | 砺波市 | となみスポーツクラブ「トライズ」 |
| 富山県 | 砺波市 | 庄川スポーツクラブ「アユーズ」 |
| 富山県 | 南砺市 | NPO法人 クラブJoy |
| 富山県 | 南砺市 | NPO法人 ふくのスポーツクラブ |
| 富山県 | 南砺市 | NPO法人 福光スポーツクラブ |
| 富山県 | 南砺市 | たいらスポーツクラブ |
| 富山県 | 南砺市 | 利賀スポーツクラブ |
| 富山県 | 入善町 | スポーツクラブ入善 |
| 富山県 | 氷見市 | スポーツプラザ ひみ |
| 富山県 | 氷見市 | ふれんず |
| 富山県 | 富山市 | NPO法人 スクエア富山 |
| 富山県 | 富山市 | (一社)パレススポーツクラブ |
| 富山県 | 富山市 | くれは総合型スポーツクラブ |
| 富山県 | 富山市 | NPO法人 五福公園スポーツクラブ さくら |
| 富山県 | 富山市 | NPO法人 きらぴか☆スポーツクラブ |
| 富山県 | 富山市 | NPO法人 中央スポーツクラブ |
| 富山県 | 富山市 | NPO法人 ひがしスポーツクラブ |
| 富山県 | 富山市 | やまだスポーツクラブ |
| 富山県 | 富山市 | NPO法人 ふちゅうスポーツクラブ |
| 富山県 | 立山町 | Rヴィレッジスポーツクラブ |
| 富山県 | 立山町 | (一社)立山連峰スポーツクラブ |
| 富山県 | 立山町 | 立山フレンドリースポーツクラブ |
| 石川県 | かほく市 | NPO法人クラブパレット |
| 石川県 | 羽咋市 | NPO法人バモスはくいスポーツクラブ |
| 石川県 | 金沢市 | NPO法人かなざわ総合スポーツクラブ |
| 石川県 | 金沢市 | NPO法人内川体育協会 |
| 石川県 | 金沢市 | NPO法人クラブぽっと |
| 石川県 | 金沢市 | ジョイナス |
| 石川県 | 七尾市 | 田鶴浜スポーツクラブ |
| 石川県 | 七尾市 | なかじまスポーツクラブ |
| 石川県 | 能登町 | 能登町スポーツクラブ設立準備委員会 |
| 石川県 | 白山市 | NPO法人ぴぃすく美川 |
| 石川県 | 宝達志水町 | NPO法人宝達スポーツ文化コミッション |
| 石川県 | 輪島市 | NPO法人もんぜんスポーツクラブ |
| 福井県 | あらわ市 | あわらトリムクラブ |
| 福井県 | おおい町 | おおい町障がいスポーツクラブ |
| 福井県 | 永平寺町 | 永平寺スポーツクラブ |
| 福井県 | 越前市 | 北日野スポーツ文化クラブ |
| 福井県 | 越前市 | 吉野総合型地域スポーツクラブ〈吉楽〉 |
| 福井県 | 越前市 | 国高総合健康クラブ |
| 福井県 | 越前市 | みなみ文化スポーツクラブ |
| 福井県 | 越前市 | えちぜんスポーツクラブ |
| 福井県 | 越前市 | 西スポーツクラブ |
| 福井県 | 越前市 | 今立総合型地域スポーツクラブ「いまスポ」 |
| 福井県 | 越前市 | 王子保すこやかスポーツクラブ |
| 福井県 | 越前市 | 越前市障がいスポーツクラブ |
| 福井県 | 高浜町 | 高浜町総合型クラブHIGH-BEACH |
| 福井県 | 坂井市 | スマイ輪ING |
| 福井県 | 坂井市 | 春江町総合型地域スポーツクラブUNITIVE291 |
| 福井県 | 鯖江市 | 特定非営利活動法人さばえスポーツクラブ |
| 福井県 | 鯖江市 | 鯖江北コミュニティースポーツクラブ |
| 福井県 | 鯖江市 | 東陽スポーツクラブ |
| 福井県 | 若狭町 | スポーツクラブわかさ |
| 福井県 | 勝山市 | NPO法人せいきコミュニティースポーツクラブ |
| 福井県 | 小浜市 | クラブアルタス |
| 福井県 | 大野市 | みんスポクラブ |
| 福井県 | 池田町 | 池田スポーツクラブ |
| 福井県 | 敦賀市 | 敦賀北スポーツクラブ |
| 福井県 | 福井市 | 清水スポーツクラブ |
| 福井県 | 福井市 | 福井フェニックス陸上(運動)クラブ |
| 福井県 | 福井市 | 特定非営利活動法人ふくいスポーツクラブ |
| 福井県 | 福井市 | 一般社団法人 総合型クラブ Fukui Sports Academy |
| 長野県 | 阿智村 | 特定非営利活動法人チャレンジゆうAc hi |
| 長野県 | 安曇野市 | 安曇野総合型地域スポーツクラブスポネット常念 |
| 長野県 | 伊那市 | 伊那市総合型地域スポーツクラプ |
| 長野県 | 栄村 | さかえスポーツクラプ |
| 長野県 | 塩尻市 | たかいで 総 合型地域スポーツクラプ |
| 長野県 | 塩尻市 | N P O 法人アンテロープアスレティ ッククラプ |
| 長野県 | 王滝村 | おうたき総合型地域スポーツクラプ |
| 長野県 | 岡谷市 | やまびこクラプ |
| 長野県 | 下條村 | 下條 文化スポーツ総合クラプ |
| 長野県 | 茅野市 | 茅野市蓼科高原スポーツクラプ |
| 長野県 | 軽井沢町 | N P O 法人スポーツコミューティー軽井沢クラプ |
| 長野県 | 御代田町 | N P O 法人あさまハイランドスポーツクラプ |
| 長野県 | 御代田町 | 総合型地域スポーツクラプ身体能力活性化広場倶楽部f u n (渠) |
| 長野県 | 香木村 | 一般社団法人たかぎスポーツクラプ |
| 長野県 | 高山村 | 高山村総合型スポーツクラプ |
| 長野県 | 高森町 | 柿の里 S , C クラプ |
| 長野県 | 佐久市 | N P O 法人もちづき総合型クラプ |
| 長野県 | 佐久市 | 岸野スポーツクラプ |
| 長野県 | 坂城町 | さかきスポーツ倶楽部 |
| 長野県 | 小諸市 | 一般社団法人浅間嶺スポーツクラプ |
| 長野県 | 小川村 | 小川スポーツふれあいクラプ |
| 長野県 | 小谷村 | 小谷村総合型地域スポーツクラプ |
| 長野県 | 小布施町 | スポーツクラプおぶせ |
| 長野県 | 小濤町南相木村・北相木村 | スポーツシューレ小海 AGGREGATO |
| 長野県 | 松本市 | N P O 法人松本山雅スポーツクラプ |
| 長野県 | 松本市 | 丸ノ内スポーツクラプ |
| 長野県 | 松本市 | s kip まつもと |
| 長野県 | 松本市 | 総合型クラプ きらり鉢盛 |
| 長野県 | 松本市 | クラプはたっこ |
| 長野県 | 松本市 | N P O 総合体操クラプ W i n g |
| 長野県 | 松本市 | M A P - 」スポーツクラプ |
| 長野県 | 上松町 | 一般社団法人木曽ひのきっ子ゆうゆうクラプ |
| 長野県 | 上田市 | N P O 法人さ なだスポーツクラプ |
| 長野県 | 上田市 | N P O法人うえだ総合型地域スポーツクラプU S C |
| 長野県 | 上田市 | オヤジ改造倶楽部 |
| 長野県 | 上田市 | N P O 法人うえだミックスポーツクラプ |
| 長野県 | 信濃町 | この指と まれ* しなの |
| 長野県 | 諏訪市 | 諏訪市ペクンククラプ |
| 長野県 | 千曲市 | 千曲アプリコットスポーツクラプ |
| 長野県 | 千曲市 | はつらつ千曲クラプ |
| 長野県 | 千曲市 | N P O法人グリーンプレイスプロジェクト |
| 長野県 | 大鹿村 | 大鹿村 総合型地域スポーツクラプ |
| 長野県 | 大町市 | N P O法人ジムナスティック・ネットワーク |
| 長野県 | 大町市 | 大町スポーツクラプ |
| 長野県 | 辰野町 | N P O 法人リュシオスポーツクラプ |
| 長野県 | 池田町 | 大かえで倶楽部 |
| 長野県 | 筑北村 | 筑北スポーツクラプ |
| 長野県 | 中野市 | 中野スマイルスポーツクラプ |
| 長野県 | 中野市 | 一般社団法人中野エスペランサスポーツクラプ |
| 長野県 | 長野市 | N P O法人長野スポーツコミュニティクラプ東北 |
| 長野県 | 長野市 | ゆたかのスポーツクラプ |
| 長野県 | 長野市 | 一般社団法人ながの北部スポーツクラプ |
| 長野県 | 長野市 | 塩崎スポーツクラプ |
| 長野県 | 長和町 | ながわスポーツクラプ |
| 長野県 | 南箕輪村 | N P O 法人南箕輪わくわくクラプ |
| 長野県 | 南木曽町 | NPO 法人 なぎそチャレンジクラプ |
| 長野県 | 白馬村 | N P O法人白馬総合型地域スポーツクラプ |
| 長野県 | 飯綱町 | いいづなスポーツクラプ |
| 長野県 | 飯山市 | 菜の花 S U Nクラプ |
| 長野県 | 飯田市 | 高陵わくわくクラプ |
| 長野県 | 飯田市 | 羽湯文化・スポーツクラプ |
| 長野県 | 飯田市 | N P O 法人南信州クラプ |
| 長野県 | 飯島町 | 飯島町 総 合型スポーツクラプ |
| 長野県 | 富士見町 | 富士見町地域スポーツクラプ |
| 長野県 | 豊丘村 | N P O 法人とよおか 総合型地域スポーツクラプ |
| 長野県 | 木島平村 | enjoy ふう太クラプ |
| 長野県 | 野沢温泉村 | 野沢温泉スキークラプ |
| 山梨県 | 甲州市 | 甲州スポーツ倶楽部 |
| 山梨県 | 甲斐市 | アスとれ総合型クラブ |
| 山梨県 | 甲斐市 | 甲斐スポーツクラブ |
| 山梨県 | 甲斐市 | グリュックスポーツクラブ |
| 山梨県 | 甲府市 | 一般社団法人 総合型地域U-SportsClub山梨 |
| 山梨県 | 山中湖村 | 山中湖スポーツクラブ |
| 山梨県 | 市川三郷町 | 特定非営利活動法人 市川三郷スポーツクラブ |
| 山梨県 | 小菅村 | みそっちょスポーツクラブ |
| 山梨県 | 昭和町 | 昭和総合型地域スポーツクラブ キャメリア |
| 山梨県 | 西桂町 | みつとうげスポーツファクトリー |
| 山梨県 | 大月市 | 大月市健やかスポーツクラブ |
| 山梨県 | 丹波山村 | タバスキースポーツクラブ |
| 山梨県 | 中央市 | NPO法人玉穂総合スポーツクラブ |
| 山梨県 | 中央市 | NPO法人ルーデンススポーツクラブ |
| 山梨県 | 笛吹市 | わいわいスポーツクラブ |
| 山梨県 | 都留市 | 都留アスリート倶楽部 |
| 山梨県 | 南アルプス市 | NPO法人トラベッソスポーツクラブ |
| 山梨県 | 南アルプス市 | NPO法人フォルトゥナスポルトクラブ |
| 山梨県 | 韮崎市 | NPO法人韮崎スポーツクラブ |
| 山梨県 | 忍野村 | 一般社団法人忍野村スポーツ振興協会 忍野スポーツクラブ |
| 山梨県 | 富士河口湖町 | 総合型地域スポーツクラブ クラブ富士山 |
| 山梨県 | 富士吉田市 | 特定非営利活動法人 富士吉田総合型地域スポーツクラブ フラックス |
| 山梨県 | 富士川町 | かじまるスポーツクラブ |
| 山梨県 | 北杜市 | ホワイトウォーターランド白州 |
| 茨城県 | かすみがうら市 | KSCエンジョイスポーツクラブ |
| 茨城県 | かすみがうら市 | KSCなかよしスポーツクラブ |
| 茨城県 | つくばみらい市 | スポーツクラブみらい |
| 茨城県 | つくば市 | NPO法人 つくばフットボールクラブ |
| 茨城県 | つくば市 | NPO法人 Next One. |
| 茨城県 | つくば市 | NPO法人 日本スポーツアカデミー |
| 茨城県 | ひたちなか市 | みなと waiwaiクラブ |
| 茨城県 | 阿見町 | 阿見いきいきクラブ |
| 茨城県 | 稲敷市 | ライフスポーツクラブしんとね |
| 茨城県 | 茨城町 | ひぬまスポーツCOM |
| 茨城県 | 下妻市 | サンドレイククラブ |
| 茨城県 | 牛久市 | 総合型地域スポーツクラブ岡田地区スポーツ交流会 |
| 茨城県 | 牛久市 | 総合型地域スポーツクラブ奥野地区スポーツ交流会 |
| 茨城県 | 牛久市 | 総合型地域スポーツクラブ牛久地区生涯スポーツ推進委員会 |
| 茨城県 | 境町 | NPO法人 境スポーツクラブ |
| 茨城県 | 結城市 | NPO法人 結城市総合型地域スポーツクラブ |
| 茨城県 | 古河市 | 特定非営利活動法人 FC古河 |
| 茨城県 | 行方市 | NPO法人 なめがたふれあいスポーツクラブ |
| 茨城県 | 坂東市 | スポーツクラブ さしま |
| 茨城県 | 桜川市 | NPO法人 桜川スマイルクラブ |
| 茨城県 | 鹿嶋市 | NPO法人 かしまスポーツクラブ |
| 茨城県 | 取手市 | NPO法人 とりで西部ふれあいクラブ |
| 茨城県 | 取手市 | NPO法人 取手セントラルクラブ |
| 茨城県 | 取手市 | NPO法人 取手東部わいわいスポーツクラブ |
| 茨城県 | 小美玉市 | NPO法人小美玉スポーツクラブ |
| 茨城県 | 城里町 | ななかいソフトスポーツクラブ |
| 茨城県 | 常総市 | 常総 スポーツクラブ |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | スポーツクラブひたまる25 |
| 茨城県 | 神栖市 | かみすスポーツクラブ |
| 茨城県 | 水戸市 | 酒門 いきいきスポーツクラブ |
| 茨城県 | 水戸市 | 一般社団法人パシオアスレチッククラブ |
| 茨城県 | 水戸市 | 一般社団法人ホーリーホックIBARAKIクラブ |
| 茨城県 | 石岡市 | NPO法人 NPO石岡総合スポーツクラブ |
| 茨城県 | 大洗町 | 夢town大洗スポーツクラブ |
| 茨城県 | 筑西市 | ASKスポーツクラブ館西 |
| 茨城県 | 潮来市 | いきいきITAKOスポーツクラブ |
| 茨城県 | 土浦市 | NPO法人 スポーツ健康支援センター土浦スポーツ健康倶楽部 |
| 茨城県 | 土浦市 | NPO法人 World Wide Dreams |
| 茨城県 | 東海村 | 東海村総合型地域スポーツクラブ スマイルTOKAI |
| 茨城県 | 那珂市 | ひまわりスポーツクラブ |
| 茨城県 | 日立市 | NPO法人 滑川 ファミリースポーツクラブ |
| 茨城県 | 日立市 | NPO法人 塙山コミュニティクラブ |
| 茨城県 | 日立市 | NPO法人UPOPO十王スポーツ文化クラブ |
| 茨城県 | 日立市 | ひたちみなみスポーツクラブ |
| 茨城県 | 美浦村 | NPO法人 ジョイナス みほ |
| 茨城県 | 鉾田市 | NPO法人 大洋スポーツクラブ |
| 茨城県 | 北茨城市 | NPO法人潮音彩レクスポ文化北茨城 |
| 茨城県 | 利根町 | とねワイワイくらぶ |
| 茨城県 | 竜ケ崎市 | NPO法人クラブ・ドラゴンズ |
| 栃木県 | さくら市 | NPO法人さくらスポーツクラブエンジョイ |
| 栃木県 | 宇都宮市 | スポルトかわち「ship」 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 友遊いずみクラブ |
| 栃木県 | 宇都宮市 | NPO法人横川スポーツクラブ |
| 栃木県 | 宇都宮市 | いきいきエンジョイ清原 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | ジョイスポしろやま |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 豊郷元気!スポーツクラブ |
| 栃木県 | 宇都宮市 | サンクスポーツクラブ陽東 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | ちゅんちゅんさわやかスポーツクラブ雀宮 |
| 栃木県 | 益子町 | ましこチャレンジクラブ |
| 栃木県 | 塩谷町 | NPO法人しおやユリピースポーツクラブ |
| 栃木県 | 下野市 | NPO法人グリムの里スポーツクラブ |
| 栃木県 | 下野市 | NPO法人夢くらぶ国分寺 |
| 栃木県 | 下野市 | 特定非営利活動法人元気ワイワイ南河内 |
| 栃木県 | 高根沢町 | 元気UPスポーツクラブ |
| 栃木県 | 高根沢町 | HOKUTO.S.C |
| 栃木県 | 佐野市 | ジョータロークラブ |
| 栃木県 | 佐野市 | 犬伏いきいきクラブ |
| 栃木県 | 佐野市 | 佐野中央スポーツクラブ |
| 栃木県 | 佐野市 | JOHOKUスポーツクラブ |
| 栃木県 | 佐野市 | NPO法人たぬまアスレチッククラブ |
| 栃木県 | 佐野市 | 葛生わいわいクラブ |
| 栃木県 | 市貝町 | 市貝いきいきクラブ |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 加蘇スポーツクラブきらら☆ |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 生子の里スポーツクラブスマイル? |
| 栃木県 | 小山市 | おにっこクラブ |
| 栃木県 | 上三川町 | かみスポクラブ |
| 栃木県 | 真岡市 | もおかスポーツクラブ |
| 栃木県 | 真岡市 | NPO法人イデア・スポーツコミュニティ |
| 栃木県 | 壬生町 | ゆうがおスポーツクラブ |
| 栃木県 | 足利市 | 三重スポーツクラブ |
| 栃木県 | 足利市 | スポーツコミュニティーとうこう |
| 栃木県 | 足利市 | 葉鹿ふれあいスポーツクラブ |
| 栃木県 | 足利市 | 三和・やまびこスポーツクラブ |
| 栃木県 | 足利市 | みくりやスポーツクラブ |
| 栃木県 | 足利市 | やまべスポーツクラブ |
| 栃木県 | 足利市 | 千歳さくら倶楽部 |
| 栃木県 | 足利市 | おまたいちょうクラブ |
| 栃木県 | 足利市 | きたごうスポーツクラブ |
| 栃木県 | 足利市 | さいこうふれあいスポーツクラブ |
| 栃木県 | 大田原市 | 大田原ジョイフルスポーツクラブ |
| 栃木県 | 大田原市 | 特定非営利活動法人 AS栃木 |
| 栃木県 | 栃木市 | NPO法人栃木スポーツネット |
| 栃木県 | 栃木市 | あいあいクラブ都賀 |
| 栃木県 | 栃木市 | いわふねスポーツクラブ |
| 栃木県 | 那珂川町 | まほろばの里スポーツクラブ |
| 栃木県 | 那須塩原市 | プレジャーランド那須 |
| 栃木県 | 那須町 | スポレクJOY那須 |
| 栃木県 | 日光市 | スポーツクラブ YOU GO! |
| 栃木県 | 日光市 | みんなで楽しむスポーツクラブ |
| 栃木県 | 日光市 | 豊岡スポーツクラブ |
| 栃木県 | 日光市 | NPO法人SCおおさわ |
| 栃木県 | 野木町 | 元気の出るスポーツクラブのぎ |
| 栃木県 | 矢板市 | NPO法人たかはら那須スポーツクラブ |
| 栃木県 | 矢板市 | チャレンジやいた |
| 栃木県 | 矢板市 | 一般社団法人矢板セントラルスポーツクラブ |
| 群馬県 | みどり市 | 大間々スポーツクラブ |
| 群馬県 | 伊勢崎市 | NPO法人伊勢崎西部スポーツクラブ |
| 群馬県 | 館林市 | 館林ジョイスポーツクラブ |
| 群馬県 | 桐生市 | NPO法人あいおいスポーツクラブ |
| 群馬県 | 吾妻郡 | 草津温泉健康クラブ |
| 群馬県 | 吾妻郡 | 中之条スポーツクラブKEYAKI |
| 群馬県 | 高崎市 | NPO法人新町スポーツクラブ |
| 群馬県 | 高崎市 | 吉井町レクリエーションクラブ |
| 群馬県 | 高崎市 | NPO法人はるなスポーツクラブ |
| 群馬県 | 高崎市 | 一般社団法人Fohlenスポーツアカデミー |
| 群馬県 | 高崎市 | NPO法人アッラヴィータスポーツクラブ |
| 群馬県 | 渋川市 | NPO法人渋川いきいき健康スポーツクラブ |
| 群馬県 | 沼田市 | うすねニュースポーツクラブ |
| 群馬県 | 沼田市 | ぬまたスポーツクラブ |
| 群馬県 | 前橋市 | 粕川スポーツクラブ |
| 群馬県 | 前橋市 | 朝倉スポーツクラブ |
| 群馬県 | 前橋市 | NPO法人宮城スポーツクラブ |
| 群馬県 | 前橋市 | NPO法人群大クラブ |
| 群馬県 | 前橋市 | 一般社団法人ホワイトスタースポーツクラブ |
| 群馬県 | 前橋市 | NPO法人ザスパスポーツクラブ |
| 群馬県 | 前橋市 | オールインスポーツクラブ |
| 群馬県 | 太田市 | おおたスポーツアカデミー(一般社団法人) |
| 群馬県 | 太田市 | 健康夢友クラブ |
| 群馬県 | 藤岡市 | NPO法人 おにし文化スポーツネット |
| 群馬県 | 藤岡市 | ふじの丘スポーツクラブ |
| 群馬県 | 北群馬郡 | しんとうスポーツクラブ |
| 群馬県 | 北群馬郡 | 吉岡総合スポーツクラブ |
| 群馬県 | 邑楽郡 | ちよだスポーツクラブ |
| 群馬県 | 邑楽郡 | めいわスポーツクラブ |
| 群馬県 | 利根郡 | NPO法人みなかみスポーツクラブ |
| 群馬県 | 利根郡 | 一般社団法人しょうわスポーツクラブ |
| 群馬県 | 利根郡 | NPO法人川場村スポーツクラブ |
| 千葉県 | 旭市 | NPO法人 スポーツアカデミー* |
| 千葉県 | 我孫子市 | 湖北はつらつクラブ* |
| 千葉県 | 我孫子市 | あびこ三小健康クラブ* |
| 千葉県 | 我孫子市 | 四小元気会* |
| 千葉県 | 鴨川市 | 鴨川オーシャンスポーツクラブ* |
| 千葉県 | 館山市 | 館山ファミリースポーツクラブわかしお* |
| 千葉県 | 君津市 | 小糸レインボークラブ* |
| 千葉県 | 四街道市 | ふれあいスポーツ佐原 |
| 千葉県 | 市原市 | 千種ふれあいくらぶ* |
| 千葉県 | 市原市 | 帝京平成スポーツアカデミー* |
| 千葉県 | 市川市 | 一般社団法人 市川スポーツガーデン国府台* |
| 千葉県 | 市川市 | 市川スポーツガーデン塩浜* |
| 千葉県 | 習志野市 | NPO法人 習志野ベイサイドスポーツクラブ* |
| 千葉県 | 習志野市 | NPO法人 習志野イースタンスポーツクラブ |
| 千葉県 | 習志野市 | NPO法人 習志野中央スポーツクラブ* |
| 千葉県 | 松戸市 | すぽ・かる小金原* |
| 千葉県 | 松戸市 | 矢切スポーツクラブ* |
| 千葉県 | 成田市 | NPO法人 成田スポーツアカデミー |
| 千葉県 | 千葉市 | NPO法人 幕張西スポーツクラブ* |
| 千葉県 | 千葉市 | ちばてんだいSV* |
| 千葉県 | 船橋市 | 大穴スポーツクラブ* |
| 千葉県 | 船橋市 | 八木が谷スポーツクラブ* |
| 千葉県 | 船橋市 | NPO法人 ならだいスポーツクラブあまなつ* |
| 千葉県 | 船橋市 | 薬円台みんなのクラブ* |
| 千葉県 | 匝瑳市 | のさかスポーツクラブ* |
| 千葉県 | 袖ヶ浦市 | NESUPO(根形スポーツクラブ)* |
| 千葉県 | 袖ヶ浦市 | NAGAX* |
| 千葉県 | 袖ケ浦市 | 中富ふれすぽクラブ* |
| 千葉県 | 銚子市 | 前宿ふれあいスポーツクラブ* |
| 千葉県 | 長生郡 | 睦沢ふれあいスポーツクラブ* |
| 千葉県 | 長生郡 | 一宮町エンジョイスポーツクラブ* |
| 千葉県 | 東金市 | 一般社団法人 東千葉スポーツクラブ |
| 千葉県 | 柏市 | NPO法人 スマイルクラブ* |
| 千葉県 | 柏市 | かしわレクスポクラブあそびん* |
| 千葉県 | 柏市 | 総合型地域スポーツクラブまちサカ |
| 千葉県 | 柏市 | 柏の葉ビーチボールクラブ |
| 千葉県 | 白石市 | 昭和ふらっとスポーツクラブ* |
| 千葉県 | 富里市 | 富里南桜クラブ* |
| 千葉県 | 茂原市 | 緑ヶ丘スポーツクラブ |
| 千葉県 | 流山市 | NPO法人 おおたかスポーツコミュニティ流山* |
| 埼玉県 | さいたま市 | NPO法人ふぁいぶるクラブ白鶴 |
| 埼玉県 | さいたま市 | NPO法人浦和スポーツクラブ |
| 埼玉県 | さいたま市 | ふれあいプレイランド |
| 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市中央スポーツクラブ |
| 埼玉県 | さいたま市 | NPO法人さいたま市地域スポーツクラブ 遊 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 南区地域スポーツクラブ |
| 埼玉県 | さいたま市 | 浦和こまばSC |
| 埼玉県 | さいたま市 | NPO法人浦和美園SCC |
| 埼玉県 | さいたま市 | 桜区地域スポーツクラブさくらっく |
| 埼玉県 | さいたま市 | NPO法人総合型地域スポーツクラブ エバースポーツ |
| 埼玉県 | さいたま市 | Cheese |
| 埼玉県 | ときがわ町 | ときがわ総合スポーツクラブ |
| 埼玉県 | ふじみ野市 | 一般社団法人ふじみ野ふぁいぶるクラブ |
| 埼玉県 | 伊奈町 | NPO法人伊奈総合型地域スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 越谷市 | NPO法人グラスルーツスポーツクラブ |
| 埼玉県 | 桶川市 | NPO法人ユニオンスポーツクラブ |
| 埼玉県 | 桶川市 | 桶川総合型地域スポーツクラブ このゆびとまれ |
| 埼玉県 | 加須市 | NPO法人フットボールクラブ加須 |
| 埼玉県 | 滑川町 | 滑川ふぁいぶるクラブ |
| 埼玉県 | 吉見町 | NPO法人武蔵丘スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 吉見町 | 吉見クラブ |
| 埼玉県 | 吉見町 | 総合型地域スポーツクラブ スポ吉 |
| 埼玉県 | 吉川市 | なまずの里クラブ |
| 埼玉県 | 久喜市 | NPO法人スポーツコミュニティ久喜 |
| 埼玉県 | 宮代町 | 総合型スポーツクラブみやしろ |
| 埼玉県 | 狭山市 | NPO法人ふぁいぶる狭山スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 熊谷市 | NPO法人熊谷リリーズ☆ふぁいぶるクラブ |
| 埼玉県 | 熊谷市 | NPO法人ピースふぁいぶるクラブ |
| 埼玉県 | 戸田市 | 総合型地域スポーツクラブとだ |
| 埼玉県 | 戸田市 | NPO法人戸田スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 戸田市 | NPO法人World Sports Family |
| 埼玉県 | 幸手市 | NPO法人クラブ幸手 |
| 埼玉県 | 行田市 | いきいき&わくわくエンジョイスポーツクラブ |
| 埼玉県 | 鴻巣市 | NPO法人鴻巣ブレス総合型スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 鴻巣市 | 笠原いきいきスポーツクラブ |
| 埼玉県 | 鴻巣市 | 川里スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 鴻巣市 | NPO法人ウォーターワイズ |
| 埼玉県 | 坂戸市 | NPO法人ウェル坂戸 |
| 埼玉県 | 三郷市 | NPO法人ふくじゅ草 |
| 埼玉県 | 三郷市 | わいわいクラブ |
| 埼玉県 | 三芳町 | 一般社団法人総合型地域スポーツクラブ絆 |
| 埼玉県 | 志木市 | NPO法人クラブしっきーず |
| 埼玉県 | 春日部市 | NPO法人ふぁいぶるクラブ春日部 |
| 埼玉県 | 春日部市 | NPO法人MGスポーツ・春日部 |
| 埼玉県 | 春日部市 | NPO法人春日部FM「かすかべフェルマータクラブ」 |
| 埼玉県 | 春日部市 | 一般社団法人1971春日部スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 所沢市 | 所沢市総合型地域スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 小鹿野町 | NPO法人ふぁいぶるクラブおがのむてっぽう |
| 埼玉県 | 松伏町 | マッピー松伏 |
| 埼玉県 | 上尾市 | NPO法人彩の国さいたま総合型地域スポーツクラブ・フォルテ |
| 埼玉県 | 上尾市 | 上尾東クラブ |
| 埼玉県 | 上尾市 | NPO法人アイウィルスポーツクラブ |
| 埼玉県 | 上里町 | NPO法人ゴールドルーツスポーツクラブ |
| 埼玉県 | 新座市 | NPO法人NAKED HEART SPORTS |
| 埼玉県 | 新座市 | NPO法人サッカースポーツ文化観光地域振興クラブ |
| 埼玉県 | 深谷市 | 一般社団法人深谷スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 深谷市 | 一般社団法人深谷スポーツ文化倶楽部 |
| 埼玉県 | 杉戸町 | NPO法人杉戸町総合型スポーツクラブすぎスポ |
| 埼玉県 | 川越市 | 芳野スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 川越市 | 川越水上公園スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 川越市 | 川越山田スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 川越市 | ふくはらスポーツクラブ |
| 埼玉県 | 川口市 | NPO法人スポーツ・サンクチュアリ・川口 |
| 埼玉県 | 川口市 | NPO法人リリー・アスレチック・クラブ |
| 埼玉県 | 川口市 | NPO法人川口戸塚総合型地域スポーツクラブ「どりーむらいふ」 |
| 埼玉県 | 川口市 | 埼玉UNITEDフットボールクラブFESTA |
| 埼玉県 | 川口市 | NPO法人フェアリースポーツクラブ |
| 埼玉県 | 川口市 | きゅぽらスポーツコミュニティ |
| 埼玉県 | 川口市 | ふぁいぶる川口芝新町スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 川口市 | 総合型地域スポーツクラブBAGUS |
| 埼玉県 | 川口市 | NPO法人SCORE 総合型地域スポーツクラブ SPROJECT F.C. |
| 埼玉県 | 川口市 | NPO法人AC フツーロ |
| 埼玉県 | 川島町 | 川島町総合型地域スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 草加市 | 総合型地域スポーツクラブ すぱえもん |
| 埼玉県 | 秩父市 | NPO法人秩父地域スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 秩父市 | ちちぶWAあいわいクラブ |
| 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | NPO法人コスモススポーツクラブ |
| 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | ふぁいぶる鶴ヶ島 |
| 埼玉県 | 東松山市 | NPO法人クラブラッキー |
| 埼玉県 | 東松山市 | 認定NPO法人東松山ペレーニアスポーツクラブ |
| 埼玉県 | 日高市 | NPO法人ZOOスポーツクラブ |
| 埼玉県 | 入間市 | 一般社団法人JOLTIVA |
| 埼玉県 | 入間市 | NPO法人オエステエス |
| 埼玉県 | 白岡市 | 篠津小総合クラブ |
| 埼玉県 | 白岡市 | NPO法人白岡Sport-Verein |
| 埼玉県 | 白岡市 | NPO法人SHIRAOKA K'sフットボールクラブ |
| 埼玉県 | 飯能市 | 飯能総合型地域スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 飯能市 | 一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミー |
| 埼玉県 | 北本市 | NPO法人あさひスポーツ・文化クラブ |
| 埼玉県 | 北本市 | NPO法人さいたま山に親しむ会 |
| 埼玉県 | 本庄市 | NPO法人神流川スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 本庄市 | 本庄スマイルスポーツクラブ |
| 埼玉県 | 毛呂山町 | 一般社団法人JAWS |
| 埼玉県 | 嵐山町 | 嵐山ふぁいぶるクラブ |
| 埼玉県 | 蓮田市 | リ・ボーンはすだ総合型地域スポーツクラブ |
| 埼玉県 | 蕨市 | 特定非営利活動法人わらびスポーツクラブ |
| 東京都 | あきる野市 | 一般社団法人あきる野総合スポーツクラブ「ASport(アスポルト)」 |
| 東京都 | あきる野市 | 五日市総合型地域スポーツクラブ |
| 東京都 | 稲城市 | NPO法人iクラブ(稲城総合型地域スポーツクラブ) |
| 東京都 | 羽村市 | 一般社団法人はむら総合型スポーツクラブはむすぽ |
| 東京都 | 葛飾区 | NPO法人こやのエンジョイくらぶ |
| 東京都 | 葛飾区 | 一般社団法人オール水元スポーツクラブ |
| 東京都 | 江東区 | NPO法人ななすぽ |
| 東京都 | 江東区 | 東陽・木場地域スポーツクラブ |
| 東京都 | 港区 | 港区総合型地域スポーツ・文化クラブ六本木(スポ-カル六本木) |
| 東京都 | 荒川区 | 南千住スポーツクラブ |
| 東京都 | 狛江市 | 狛江市総合型スポーツ・文化クラブ「狛○(WA)くらぶ」 |
| 東京都 | 三鷹市 | 三鷹ウエストスポーツクラブ |
| 東京都 | 渋谷区 | 一般社団法人渋谷ほんまちクラブ |
| 東京都 | 小金井市 | NP0法人黄金井倶楽部 |
| 東京都 | 昭島市 | 昭島くじらスポーツクラブ |
| 東京都 | 新宿区 | 新宿チャレンジスポーツ文化クラブ |
| 東京都 | 瑞穂町 | ミズホ笑夢(エム)スポーツクラブ |
| 東京都 | 杉並区 | 向陽スポーツ文化クラブ |
| 東京都 | 杉並区 | クラブ123荻窪 |
| 東京都 | 世田谷区 | 東深沢スポーツ・文化クラブ |
| 東京都 | 世田谷区 | 烏山スポーツクラブユニオン |
| 東京都 | 世田谷区 | しろやま倶楽部 |
| 東京都 | 世田谷区 | こまざわスポーツ・文化クラブ |
| 東京都 | 西東京市 | にしはらスポーツクラブ |
| 東京都 | 足立区 | KITクラブ21 |
| 東京都 | 足立区 | U&Uクラブ |
| 東京都 | 足立区 | 興本倶楽部 |
| 東京都 | 足立区 | SUK2クラブ |
| 東京都 | 足立区 | NACKクラブ |
| 東京都 | 大田区 | NPO法人地域総合スポーツ倶楽部・ピボットフット |
| 東京都 | 大田区 | 一般社団法人田園調布グリーンコミュニティ |
| 東京都 | 大田区 | NPO法人スマイルかまた |
| 東京都 | 中央区 | 一般社団法人中央区地域スポーツクラブ大江戸月島 |
| 東京都 | 町田市 | NPO法人法政クラブ |
| 東京都 | 調布市 | NPO法人調和SHC倶楽部 |
| 東京都 | 日野市 | 一般社団法人平和台文化スポーツクラブ |
| 東京都 | 八王子市 | 恩方夕やけスポーツクラブ |
| 東京都 | 八王子市 | NPO法人はちきたSC |
| 東京都 | 八王子市 | 第三地区スポーツクラブ運営委員会 |
| 東京都 | 八王子市 | 第八地区スポーツクラブ運営協議会 |
| 東京都 | 八王子市 | 加住地区総合型スポーツクラブ |
| 東京都 | 板橋区 | NPO法人志村スポーツクラブ・プリムラ |
| 東京都 | 府中市 | 府中市総合型f-エフ- スポーツクラブ |
| 東京都 | 武蔵村山市 | よってかっしぇクラブ |
| 東京都 | 文京区 | 礫南スポーツクラブ |
| 東京都 | 豊島区 | NPO法人地域総合型椎の美スポーツクラブ |
| 東京都 | 豊島区 | 西巣鴨中学校地域スポーツクラブ |
| 東京都 | 北区 | NPO法人れっど★しゃっふる |
| 東京都 | 目黒区 | NPO法人スポルテ目黒 |
| 東京都 | 練馬区 | NPO法人コミュニティネットSSC大泉 |
| 東京都 | 練馬区 | NPO法人スポーツコミュニティー桜 |
| 東京都 | 練馬区 | NPO法人総合型地域スポーツクラブ平和台 |
| 東京都 | 練馬区 | NPO法人スポーツクラブホワイエ上石神井 |
| 東京都 | 練馬区 | NPO法人豊玉・中村地域スポーツクラブクラブプラッツ |
| 神奈川県 | 愛甲郡愛川町 | NPO法人 きよかわアウトドアスポーツクラブ |
| 神奈川県 | 愛甲郡清川町 | 相模原スポーツアカデミー(SSA) |
| 神奈川県 | 綾瀬市 | 一般社団法人 愛川ウエルネスネットワーク |
| 神奈川県 | 伊勢原市 | NPO法人 AZスポーツクラブ |
| 神奈川県 | 伊勢原市 | 開成町総合型スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 横須賀市 | NPO法人 横須賀シーガルズ・スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 横須賀市 | NPO法人 よこすか総合型地域スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 横須賀市 | NPO法人 湘南ルベントスポーツクラブ |
| 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見スポーツ&カルチャークラブ |
| 神奈川県 | 横浜市 | NPO法人 かながわクラブ |
| 神奈川県 | 横浜市 | KAZU SPORTS CLUB |
| 神奈川県 | 横浜市 | はざわクラブ |
| 神奈川県 | 横浜市 | NPO法人 横浜かもめanimaクラブ |
| 神奈川県 | 横浜市 | まる倶楽部 |
| 神奈川県 | 横浜市 | NPO法人 ライフネットスポーツクラブ |
| 神奈川県 | 横浜市 | NPO法人 横浜スポーツアンドカルチャークラブ |
| 神奈川県 | 横浜市 | 弘明寺くらぶ |
| 神奈川県 | 横浜市 | カンガルークラブ |
| 神奈川県 | 横浜市 | 新井中学校文化・スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 横浜市 | NPO法人 若葉台スポーツ・文化クラブ |
| 神奈川県 | 横浜市 | NPO法人 横濱ラグビーアカデミー |
| 神奈川県 | 横浜市 | 金沢スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 横浜市 | やましたスポーツ・文化クラブ |
| 神奈川県 | 横浜市 | NPO法人 CLUB TEATRO |
| 神奈川県 | 横浜市 | くろがね倶楽部 |
| 神奈川県 | 横浜市 | NPO法人 わくわく教室 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 都筑スポーツプランナー竹の子会 |
| 神奈川県 | 横浜市 | クローバースポーツクラブ |
| 神奈川県 | 横浜市 | さかえスポーツくらぶ |
| 神奈川県 | 横浜市 | 緑園スポーツ・文化クラブ |
| 神奈川県 | 横浜市 | NPO葛野スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 横浜市 | 一般社団法人横浜FC総合型地域スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 横浜市 | NPO法人トータルライフサポートクラブ |
| 神奈川県 | 鎌倉市 | 一般社団法人 善行・大越スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 茅ヶ崎総合型スポーツクラブ“YOU悠” |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | NPO法人 SUERTE |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | (財)逗子市体育協会スポーツクラブ「うみかぜクラブ」 |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 江ノ島ちょっとヨットビーチクラブ |
| 神奈川県 | 厚木市 | NPO法人 おおねスポーツコミュニティ |
| 神奈川県 | 高座郡寒川町 | NPO法人 パーム・インターナショナル湘南 |
| 神奈川県 | 座間市 | NPO法人 綾瀬スポーツコミュニティ |
| 神奈川県 | 三浦市 | NPO法人 湘南ベルマーレスポーツクラブ |
| 神奈川県 | 小田原市 | 城下町スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 小田原市 | 東海大学健康クラブ |
| 神奈川県 | 秦野市 | 伊勢原・ふれすぽ |
| 神奈川県 | 逗子市 | NPO法人 スポーツクラブ1994 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 川中島総合型スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 川崎市 | 幸総合型スポーツクラブPLUM |
| 神奈川県 | 川崎市 | 平間スポーツレクリエーションクラブ |
| 神奈川県 | 川崎市 | NPO法人 かわさきスポーツドリーマーズ |
| 神奈川県 | 川崎市 | NPO法人 高津総合型スポーツクラブSELF |
| 神奈川県 | 川崎市 | 菅生スポーツ・コミュニティクラブ |
| 神奈川県 | 川崎市 | NPO法人 中野島総合型スポーツクラブビルネ |
| 神奈川県 | 川崎市 | 金程中学校区わ・わ・わ・クラブ |
| 神奈川県 | 川崎市 | 中原元気クラブ |
| 神奈川県 | 川崎市 | ファンズスポーツクラブ宮前 |
| 神奈川県 | 川崎市 | 馬堀スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 相模原市 | 大沢FC総合型地域スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 相模原市 | NPO法人 相模原フットボールクラブ |
| 神奈川県 | 相模原市 | NPO法人 FCコラソン |
| 神奈川県 | 相模原市 | 総合型地域まちづくり文化スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 相模原市 | NPO法人 SRC(スポーツレクリエーションコミュニティ) |
| 神奈川県 | 相模原市 | やんちゃるジム |
| 神奈川県 | 相模原市 | NPO法人 ミハタ |
| 神奈川県 | 相模原市 | あそべーる大沼クラブ |
| 神奈川県 | 相模原市 | 相模原ライズ・アスリート・クラブ |
| 神奈川県 | 相模原市 | NPO法人 Vidaスポーツクラブいさま |
| 神奈川県 | 相模原市 | 一般社団法人SCDスポーツクラブ |
| 神奈川県 | 相模原市 | NPO法人ベーススポーツ |
| 神奈川県 | 相模原市 | 大和スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 星槎箱根仙石原総合型スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 松田ゆいスポーツクラブ |
| 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | NPO法人 スポーツコミュニティ・シュート |
| 神奈川県 | 足柄上郡山北町 | NPO法人 城山スポーツ&カルチャークラブめいぷる |
| 神奈川県 | 足柄上郡松田町 | 一般社団法人 あすぽ |
| 神奈川県 | 大和市 | NPO法人大和シルフィード・スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 大和市 | やまとスポーツマネジメント設立準備会 |
| 神奈川県 | 中郡大磯町 | 星槎湘南大磯総合型スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 藤沢市 | NPO法人 パシフィックビーチクラブ |
| 神奈川県 | 藤沢市 | NPO法人藤沢ラグビー蹴球倶楽部 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 三浦スポーツ&カルチャークラブ |
| 神奈川県 | 南足柄市 | NPO法人 大磯うみくらぶ |
| 神奈川県 | 平塚市 | 寒川総合スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 平塚市 | 港スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 平塚市 | NPO法人 W.O.F平塚総合型地域スポーツクラブ |
| 神奈川県 | 平塚市 | 小田原フレンドリークラブ |
| 神奈川県 | 平塚市 | 湘南シーホーススポーツクラブ |
| 静岡県 | 掛川市 | NPO法人掛川市体育協会(掛川総合スポーツクラブ) |
| 静岡県 | 菊川市 | アプロス菊川 |
| 静岡県 | 御殿場市 | 御殿場総合スポーツクラブ |
| 静岡県 | 三島市 | 特定非営利活動法人 エンジョイスポーツ三島 |
| 静岡県 | 沼津市 | 一般社団法人 アスルクラロスポーツクラブ |
| 静岡県 | 榛原郡川根本町 | かわねライフスポーツクラブ |
| 静岡県 | 静岡市駿河区 | 特定非営利活動法人 エートススポーツフィールド |
| 静岡県 | 島田市 | プラスワン |
| 静岡県 | 藤枝市 | NPO法人大洲スポーツクラブ |
| 静岡県 | 藤枝市 | 藤枝東スポーツクラブ |
| 静岡県 | 藤枝市 | SCりゅうせい |
| 静岡県 | 磐田市 | 竜洋スポーツクラブ |
| 静岡県 | 磐田市 | 静岡産業大学いわた総合スポーツクラブ |
| 静岡県 | 浜松市天竜区 | 総合型地域スポーツクラブ 天竜楽漕クラブ |
| 静岡県 | 浜松市天竜区 | みさくぼスポーツクラブ |
| 静岡県 | 富士宮市 | 宮keiスポーツクラブ |
| 静岡県 | 富士市 | 総合型地域スポーツクラブ F-SPO |
| 静岡県 | 牧之原市 | まきのはら総合スポーツクラブ |
| 愛知県 | あま市 | あまスポーツクラブ |
| 愛知県 | みよし市 | 三好さんさんスポーツクラブ |
| 愛知県 | 安城市 | NPO法人JOANスポーツクラブ |
| 愛知県 | 一宮市 | NPO法人木曽川文化・スポーツクラブ |
| 愛知県 | 江南市 | スポーツクラブ江南 |
| 愛知県 | 高浜市 | NPO法人たかはまスポーツクラブ |
| 愛知県 | 瀬戸市 | 水野・西陵いきいきクラブ |
| 愛知県 | 清須市 | きよすスポーツクラブ |
| 愛知県 | 西尾市 | NPO法人スポーツクラブいっしき |
| 愛知県 | 大口町 | NPO法人ウィル大口スポーツクラブ |
| 愛知県 | 大治町 | スポーツプラスおおはる |
| 愛知県 | 大府市 | OBUエニスポ |
| 愛知県 | 知立市 | 知立みなみスポーツ・文化クラブ |
| 愛知県 | 長久手町 | がんばらっせ長久手スポーツクラブ |
| 愛知県 | 田原市 | なのはなスポーツクラブ |
| 愛知県 | 扶桑町 | NPO法人わっと楽らくスポーツふそう |
| 愛知県 | 豊田市 | NPO法人かみごうスポーツクラブ |
| 愛知県 | 豊田市 | 高橋スポーツクラブ |
| 愛知県 | 豊田市 | しもやまスポーツクラブ |
| 愛知県 | 豊田市 | (一社)梅坪・浄水スポーツクラブ |
| 愛知県 | 豊田市 | すえのはらスポーツクラブ |
| 愛知県 | 豊田市 | 逢妻スポーツクラブ |
| 愛知県 | 名古屋市 | NPO法人愛知スポーツ倶楽部 |
| 愛知県 | 名古屋市 | NPO法人名古屋スポーツクラブ |
| 愛知県 | 弥富市 | NPO法人やとみスポーツクラブ |
| 愛知県 | 蟹江町 | NPO法人活き生きかにえスポーツクラブ |
| 愛知県 | 飛島村 | スポーツクラブとびしま |
| 愛知県 | 東浦町 | NPO法人森と川スポーツクラブ |
| 愛知県 | 武豊町 | NPO法人ゆめフルたけとよスポーツクラブ |
| 岐阜県 | 安八町 | NPO法人総合体操クラブ |
| 岐阜県 | 羽島市 | はしまモアスポーツクラブ |
| 岐阜県 | 羽島市 | はしまなごみスポーツクラブ |
| 岐阜県 | 羽島市 | はしま南部スポーツ村 |
| 岐阜県 | 下呂市 | NPO法人萩原スポーツクラブ |
| 岐阜県 | 可児市 | 可児UNICスポーツクラブ |
| 岐阜県 | 海津市 | スマイルクラブこん平田 |
| 岐阜県 | 海津市 | 一般社団法人南濃スポーツクラブ |
| 岐阜県 | 関市 | せきスポーツクラブ |
| 岐阜県 | 関市 | NPO法人キウイスポーツクラブ |
| 岐阜県 | 関市 | 上之保ほほえみスポーツクラブ |
| 岐阜県 | 関市 | 一般社団法人せき西部ふれあいスポーツクラブ |
| 岐阜県 | 岐南町 | NPO法人スポーツ振興協議会 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 精華スポーツクラブ |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 長森・日野スポーツクラブ |
| 岐阜県 | 岐阜市 | みわスポーツクラブ |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 長良西スポーツクラブ |
| 岐阜県 | 岐阜市 | NPO法人FC10min |
| 岐阜県 | 岐阜市 | やないづスポーツクラブ |
| 岐阜県 | 郡上市 | NPO法人スポーツフラッグG |
| 岐阜県 | 郡上市 | 一般社団法人郡上ブルーズスポーツクラブ |
| 岐阜県 | 恵那市 | えなイースト総合スポーツクラブ |
| 岐阜県 | 恵那市 | あけちクラブ |
| 岐阜県 | 御嵩町 | 一般社団法人みたけスポーツ・文化倶楽部 |
| 岐阜県 | 坂祝町 | 坂祝スポーツクラブ |
| 岐阜県 | 山県市 | NPO法人たかとみスポーツクラブ |
| 岐阜県 | 神戸町 | NPO法人ごうどスポーツクラブ |
| 岐阜県 | 垂井町 | NPO法人Let‘sたるい |
| 岐阜県 | 瑞穂市 | NPO法人Link-upみずほ |
| 岐阜県 | 瑞穂市 | 公益社団法人ぎふ瑞穂スポーツガーデン |
| 岐阜県 | 瑞浪市 | NPO法人稲津スポーツ・文化クラブ |
| 岐阜県 | 川辺町 | 川辺スポーツクラブ |
| 岐阜県 | 大垣市 | NPO法人FCヴィオーラ |
| 岐阜県 | 池田町 | NPO法人いけだスポーツクラブ |
| 岐阜県 | 中津川市 | 認定NPO法人つけちスポーツクラブ |
| 岐阜県 | 中津川市 | NPO法人やさかイキイキ倶楽部 |
| 岐阜県 | 中津川市 | NPO法人Viva!中津川 |
| 岐阜県 | 東白川村 | NPO法人青空見聞塾 |
| 岐阜県 | 白川町 | 一般社団法人スポーツリンク白川 |
| 岐阜県 | 八百津町 | チャレンジクラブ802 |
| 岐阜県 | 飛騨市 | 一般社団法人飛騨シューレ |
| 岐阜県 | 北方町 | きらり北方クラブ |
| 岐阜県 | 本巣市 | スポーツクラブもとす |
| 岐阜県 | 輪之内町 | 輪之内スポーツクラブ |
| 三重県 | 伊賀市 | 一般社団法人 府中スポーツクラブ |
| 三重県 | 伊賀市 | かんべスポーツクラブ |
| 三重県 | 伊賀市 | 猪田らくらくクラブ |
| 三重県 | 伊賀市 | NPO法人 いがまちスポーツクラブ |
| 三重県 | 伊賀市 | NPO法人 伊賀フューチャーズクラブ |
| 三重県 | 伊賀市 | おおやまだスポーツクラブ |
| 三重県 | 伊勢市 | いすずウキウキクラブ |
| 三重県 | 伊勢市 | 厚生総合型スポーツクラブ |
| 三重県 | 伊勢市 | おばたスポレククラブASREC |
| 三重県 | 伊勢市 | ふたみふれ愛クラブ |
| 三重県 | 亀山市 | NPO法人 Let'sスポーツわくわくらぶ |
| 三重県 | 玉城町 | たまき文化スポーツクラブ |
| 三重県 | 熊野市 | くまの健康スポーツクラブ |
| 三重県 | 熊野市 | ふれあいスポーツクラブ紀和 |
| 三重県 | 桑名市 | スポーツステーション多度 |
| 三重県 | 菰野町 | NPO法人 元気アップこものスポーツクラブ |
| 三重県 | 四日市市 | NPO法人 四日市ウェルネスクラブ |
| 三重県 | 四日市市 | NPO法人 楠スポーツクラブ |
| 三重県 | 志摩市 | NPO法人 いそべスポーツクラブ |
| 三重県 | 志摩市 | NPO法人 志摩スポーツクラブ |
| 三重県 | 志摩市 | NPO法人 浜島スポーツクラブ |
| 三重県 | 松阪市 | まつさかTAIKYOスポーツクラブ |
| 三重県 | 川越町 | 川越FAGクラブ |
| 三重県 | 鳥羽市 | 長岡スポーツ文化クラブ |
| 三重県 | 津市 | 西橋内文化・スポーツクラブ |
| 三重県 | 津市 | かわげスポーツクラブ |
| 三重県 | 津市 | 橋南スポーツクラブ |
| 三重県 | 津市 | NPO法人 あのうスポーツクラブ |
| 三重県 | 度会町 | 度会スポーツクラブ |
| 三重県 | 東員町 | とういんフレンドリークラブ |
| 三重県 | 尾鷲市 | 尾鷲スポーツクラブ |
| 三重県 | 木曽岬町 | 特定非営利活動法人 きそさきAZクラブ |
| 三重県 | 鈴鹿市 | 一般社団法人 鈴鹿大学スポーツアカデミー |
| 滋賀県 | 愛荘町 | NPO法人 ジョイスポ・はたしょう |
| 滋賀県 | 愛荘町 | Eスポ・えちがわ |
| 滋賀県 | 栗東市 | 治西ゆうあいスポーツクラブ |
| 滋賀県 | 栗東市 | 総合型クラブ NPO法人りっとう |
| 滋賀県 | 湖南市 | 湖南市ちょいスポクラブ |
| 滋賀県 | 甲賀市 | はーと貴生川スポーツクラブ |
| 滋賀県 | 甲賀市 | 伴谷BANBANクラブ |
| 滋賀県 | 甲賀市 | NPO法人 レインボークラブ |
| 滋賀県 | 甲賀市 | NPO法人 こうかサスケくらぶ |
| 滋賀県 | 甲賀市 | ぽぽんた倶楽部 |
| 滋賀県 | 甲賀市 | KOHNAN忍にんスポーツクラブ |
| 滋賀県 | 甲賀市 | 綾野ゆうゆうクラブ |
| 滋賀県 | 甲賀市 | 城山あいあいクラブ |
| 滋賀県 | 高島市 | 一般社団法人 いまづジョイナスクラブ |
| 滋賀県 | 高島市 | 認定NPO法人 TSC |
| 滋賀県 | 守山市 | ハヤノクラブ |
| 滋賀県 | 守山市 | 吉身立入が丘スポーツクラブ |
| 滋賀県 | 守山市 | 小津クラブ |
| 滋賀県 | 草津市 | NPO法人 くさつ健・交クラブ |
| 滋賀県 | 多賀町 | NPO法人 多賀やまびこクラブ |
| 滋賀県 | 大津市 | 大津市体育協会総合型地域スポーツクラブ |
| 滋賀県 | 大津市 | NPO法人 瀬田漕艇倶楽部 |
| 滋賀県 | 大津市 | NPO法人 BIWAKO SPORTS CLUB |
| 滋賀県 | 大津市 | NPO法人 スポーツクラブSETA |
| 滋賀県 | 長浜市 | きのもとeye's |
| 滋賀県 | 長浜市 | 奥びわ湖スポーツクラブ |
| 滋賀県 | 長浜市 | 高月総合型スポーツクラブ ピース |
| 滋賀県 | 長浜市 | 余呉はごろもクラブ |
| 滋賀県 | 長浜市 | 長浜スポーツコミュニティクラブ |
| 滋賀県 | 長浜市 | こほくEクラブ |
| 滋賀県 | 長浜市 | とらひめ総合型スポーツクラブ |
| 滋賀県 | 長浜市 | びわスポーツクラブ |
| 滋賀県 | 長浜市 | AZAIお市クラブ |
| 滋賀県 | 東近江市 | あかねスポーツクラブ |
| 滋賀県 | 東近江市 | コミスポようかいち |
| 滋賀県 | 東近江市 | あいとうスポーツクラブ |
| 滋賀県 | 東近江市 | 健康倶楽部ごかしょう |
| 滋賀県 | 東近江市 | ことう健康夢クラブ |
| 滋賀県 | 東近江市 | NPO法人 能登川総合スポーツクラブ |
| 滋賀県 | 東近江市 | 奥永源寺スポーツクラブ |
| 滋賀県 | 彦根市 | 彦クラブ |
| 滋賀県 | 彦根市 | NPO法人 エスピロッサ |
| 滋賀県 | 米原市 | NPO法人 MOSスポーツクラブ |
| 滋賀県 | 米原市 | いぶきスポーツクラブ |
| 滋賀県 | 米原市 | NPO法人 カモンスポーツクラブ |
| 滋賀県 | 豊郷町 | NPO法人 アザックとよさと |
| 滋賀県 | 野洲市 | さざなみスポーツクラブ |
| 滋賀県 | 野洲市 | NPO法人YASUほほえみクラブ |
| 滋賀県 | 竜王町 | ドラゴンスポーツクラブ |
| 奈良県 | 安堵町 | すこやか安堵スポーツクラブ |
| 奈良県 | 宇陀市 | フレッシュアップ榛原 |
| 奈良県 | 王寺町 | 総合型地域倶楽部 王寺やわらぎトラスト |
| 奈良県 | 下市町 | 下市町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(仮称) |
| 奈良県 | 下市町 | NPO法人 ここサポ |
| 奈良県 | 下北山村 | 下北山村総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(仮称) |
| 奈良県 | 河合町 | 河合町総合型地域スポーツクラブ |
| 奈良県 | 橿原市 | NPO法人 ポルベニルカシハラスポーツクラブ |
| 奈良県 | 橿原市 | NPO法人 香久山総合型スポーツクラブ |
| 奈良県 | 橿原市 | NPO法人 橿原健康スポーツクラブKKSC |
| 奈良県 | 葛城市 | スポーツクラブ葛城 |
| 奈良県 | 吉野町 | NPO法人 吉野スポーツクラブ |
| 奈良県 | 五條市 | 五條スポーツクラブ設立準備委員会(仮称) |
| 奈良県 | 御所市 | NPO法人 御所スポーツクラブ |
| 奈良県 | 御杖村 | 御杖村総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(仮称) |
| 奈良県 | 広陵町 | 広陵ステーションプラス1クラブ |
| 奈良県 | 香芝市 | 香芝市総合型地域スポーツクラブレッツかしば! |
| 奈良県 | 香芝市 | NPO法人 ACES |
| 奈良県 | 高取町 | 高取町総合型地域スポーツクラブ メープルクラブ |
| 奈良県 | 黒滝村 | 黒滝村総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(仮称) |
| 奈良県 | 桜井市 | 芝運動公園スポーツクラブ |
| 奈良県 | 桜井市 | 安倍体育協会スポーツクラブ |
| 奈良県 | 桜井市 | 大福地域スポーツクラブ |
| 奈良県 | 桜井市 | 桜井南ふれあいクラブ |
| 奈良県 | 三郷町 | 一般社団法人元気ひまわりクラブ三郷 |
| 奈良県 | 三宅町 | 三宅ゆるスポクラブ |
| 奈良県 | 山添村 | 奈良アスレチックス山添 |
| 奈良県 | 十津川村 | 十津川村総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(仮称) |
| 奈良県 | 上北山村 | 上北山村総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(仮称) |
| 奈良県 | 上牧町 | 里風総合型クラブ上牧 |
| 奈良県 | 生駒市 | NPO法人 プロストリート関西 |
| 奈良県 | 生駒市 | いこ増ッスルクラブ |
| 奈良県 | 生駒市 | 一般社団法人リトルパイン総合型地域スポーツクラブ |
| 奈良県 | 川上村 | 川上村総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(仮称) |
| 奈良県 | 川西町 | NPO法人 川西スポーツクラブ |
| 奈良県 | 曽爾村 | 曽爾村総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(仮称) |
| 奈良県 | 大淀町 | 大淀町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(仮称) |
| 奈良県 | 大和郡山市 | NPO法人 大和ふれあいスポーツクラブ |
| 奈良県 | 大和郡山市 | 大和郡山AC |
| 奈良県 | 大和高田市 | リアルスタイル高田スポーツクラブ |
| 奈良県 | 天理市 | NPO法人 前栽校区ゆうゆうクラブ |
| 奈良県 | 天理市 | 天南クラブ |
| 奈良県 | 天理市 | 天理総合YYクラブ |
| 奈良県 | 田原本町 | NPO法人 青垣すまいるクラブ |
| 奈良県 | 東吉野村 | 東吉野村総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(仮称) |
| 奈良県 | 奈良市 | 平城ニュータウンスポーツ協会 |
| 奈良県 | 奈良市 | NPO法人 ソレステレージャ奈良2002 |
| 奈良県 | 奈良市 | NPO法人 ならスポーツクラブ |
| 奈良県 | 奈良市 | 鴻ノ池スポーツクラブ |
| 奈良県 | 奈良市 | NPO法人 奈良クラブ |
| 奈良県 | 奈良市 | NPO法人 グラミーゴ奈良三笠 |
| 奈良県 | 奈良市 | NPO法人 スクデットスポーツプランニング |
| 奈良県 | 奈良市 | みあと総合型スポーツクラブ設立準備委員会(仮称) |
| 奈良県 | 奈良市 | あきしの総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会(仮称) |
| 奈良県 | 斑鳩町 | NPO法人 元気クラブいかるが |
| 奈良県 | 平群町 | 一般社団法人くまがしクラブ |
| 奈良県 | 明日香村 | NPO法人 楽スポあすか |
| 京都府 | 井手町 | IDEゆうゆうスポーツクラブ |
| 京都府 | 宇治市 | NPO法人東宇治スポーツクラブ |
| 京都府 | 宇治市 | 太陽が丘スポーツクラブ |
| 京都府 | 宇治市 | 京都文教大学地域スポーツクラブ |
| 京都府 | 亀岡市 | 南つつじヶ丘スポーツクラブ |
| 京都府 | 亀岡市 | 千歳七福神スポーツクラブ |
| 京都府 | 亀岡市 | ひえよしクラブ |
| 京都府 | 亀岡市 | ASAHIスポーツクラブ |
| 京都府 | 宮津市 | NPO法人Sports Club RAINBOW |
| 京都府 | 京丹後市 | 久美浜スポーツクラブ |
| 京都府 | 京丹後市 | NPO法人網野スポーツクラブ |
| 京都府 | 京丹波町 | 桧山わいわいクラブ |
| 京都府 | 京丹波町 | 質美スポーツクラブかがやき |
| 京都府 | 京丹波町 | 三ノ宮さんさんクラブ |
| 京都府 | 京丹波町 | 梅田げんき村 |
| 京都府 | 京丹波町 | 丹波スポーツクラブ |
| 京都府 | 京丹波町 | 京丹波町スポーツクラブ |
| 京都府 | 京田辺市 | 京たなべ・同志社スポーツクラブ |
| 京都府 | 京都市 | 京北スポーツクラブ |
| 京都府 | 京都市 | 京都教育大学地域スポーツクラブ |
| 京都府 | 京都市 | K-style |
| 京都府 | 京都市 | NPO法人紫明倶楽部 |
| 京都府 | 京都市 | 京都外大クラブ |
| 京都府 | 京都市 | NPO法人京都日野匠スポーツクラブ |
| 京都府 | 京都市 | NPO法人サニースポーツクラブ京都 |
| 京都府 | 向日市 | 向日市ワイワイスポーツクラブ |
| 京都府 | 城陽市 | 寺田西総合型地域スポーツクラブ |
| 京都府 | 長岡京市 | 総合型長七みんなのスポーツクラブ |
| 京都府 | 長岡京市 | フォー遊クラブ |
| 京都府 | 長岡京市 | ふるさとスポーツクラブ |
| 京都府 | 長岡京市 | 長五校区総合型地域スポーツクラブ |
| 京都府 | 長岡京市 | グッド楽クラブ |
| 京都府 | 長岡京市 | 倶楽部・てん |
| 京都府 | 長岡京市 | さんSUNスポレククラブ |
| 京都府 | 長岡京市 | 8スルくらぶ |
| 京都府 | 南山城村 | 南山城村お茶っぴクラブ |
| 京都府 | 南丹市 | 日吉総合型地域スポーツクラブ |
| 京都府 | 南丹市 | 富本クラブ |
| 京都府 | 南丹市 | みやまスポーツクラブ |
| 京都府 | 南丹市 | そのべ総合型地域スポーツクラブ |
| 京都府 | 舞鶴市 | 舞鶴ちゃったスポーツクラブ |
| 京都府 | 福知山市 | 福知山スポーツクラブ |
| 京都府 | 福知山市 | 鬼楽スポーツクラブ |
| 京都府 | 与謝野町 | かやスポーツクラブ |
| 京都府 | 与謝野町 | 野田川スポーツクラブ |
| 京都府 | 和束町 | 和束スポーツクラブ |
| 大阪府 | 茨木市 | 認定NPO法人茨木東スポーツクラブ レッツ |
| 大阪府 | 茨木市 | 特定非営利活動法人茨木北スポーツクラブ オーク |
| 大阪府 | 河内?野市 | 特定非営利活動法人?野総合スポーツクラブ |
| 大阪府 | 岸和田市 | 特定非営利活動法人FC岸和田 |
| 大阪府 | 高石市 | きらり総合クラブたかいし |
| 大阪府 | 阪南市 | 阪南AC |
| 大阪府 | 堺市 | クラブ登美丘南 |
| 大阪府 | 松原市 | スポーツクラブ松原中央 |
| 大阪府 | 松原市 | ふれあいスマイルクラブ |
| 大阪府 | 松原市 | 三宅スポーツ文化クラブ |
| 大阪府 | 寝屋川市 | 池の里クラブ |
| 大阪府 | 摂津市 | 特定非営利活動法人せっつブルーウィングス |
| 大阪府 | 泉大津市 | 泉大津市総合型地域スポーツクラブOZUスポ |
| 大阪府 | 大阪狭山市 | NPO法人大阪狭山スポーツクラブ |
| 大阪府 | 大阪市 | たつみスポーツクラブ |
| 大阪府 | 大東市 | 特定非営利活動法人いきいき大東スポーツクラブ |
| 大阪府 | 島本町 | 特定非営利活動法人しまもとバンブークラブ |
| 大阪府 | 東大阪市 | NPO法人三ノ瀬総合型スポーツクラブ |
| 大阪府 | 柏原市 | 大阪教育大学スポーツクラブ |
| 大阪府 | 豊中市 | てしま総合型ローズクラブ |
| 大阪府 | 枚方市 | ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブ |
| 大阪府 | 箕面市 | 箕面東コミュニティスポーツクラブ |
| 大阪府 | 箕面市 | 箕面SC |
| 大阪府 | 岬町 | 岬町総合型地域スポーツクラブみさきタコクラブ |
| 大阪府 | 門真市 | 特定非営利活動法人門真はすねクラブ |
| 兵庫県 | 丹波市 | (スポ-ツクラブ21新井) あかつきクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | GENKI西脇スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | KASUMIスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(兵庫区) | KOBE GION SC |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | Lily Bell スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 播磨町 | NPO法人スポーツクラブ21はりま |
| 兵庫県 | 加古川市 | NPO法人加古川総合スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | OH☆いけっ!!スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | あいなスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | アスリートクラブ福田 |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | ありの台スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | いたやどGENKIクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | いぶきウエストスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | いぶきの丘スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | いぶき東スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 丹波市 | カモカモクラブ(スポ-ツクラブ21鴨庄) |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | からとクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | こでらスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | スポーツ21竹の台クラブ |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツandカルチャークラブ21苦楽園 |
| 兵庫県 | 朝来市 | スポーツクラブ21 ITOI |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21・福良 |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21・北阿万 |
| 兵庫県 | 養父市 | スポーツクラブ21sekinomiya |
| 兵庫県 | 芦屋市 | スポーツクラブ21YAMATE |
| 兵庫県 | 相生市 | スポーツクラブ21あいおい |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21あいはし |
| 兵庫県 | 洲本市 | スポーツクラブ21あいはら |
| 兵庫県 | 相生市 | スポーツクラブ21あおば |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21あかしあ台 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21あがほ |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21あくら |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21あくら北 |
| 兵庫県 | 朝来市 | スポーツクラブ21あさご(山口) |
| 兵庫県 | 朝来市 | スポーツクラブ21あさご(中川) |
| 兵庫県 | 養父市 | スポーツクラブ21あざの |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21あじま |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21あぞの |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21あなが |
| 兵庫県 | 香美町 | スポーツクラブ21あまるべ |
| 兵庫県 | 神河町 | スポーツクラブ21あわが |
| 兵庫県 | 朝来市 | スポーツクラブ21あわが |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21あわじ |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21いえしま |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21いかり |
| 兵庫県 | 朝来市 | スポーツクラブ21いくの |
| 兵庫県 | 新温泉町 | スポーツクラブ21いぐみ |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21いけじり |
| 兵庫県 | 加西市 | スポーツクラブ21いずみ |
| 兵庫県 | 香美町 | スポーツクラブ21いそう |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21いたみ |
| 兵庫県 | 小野市 | スポーツクラブ21いちば |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21いとひき |
| 兵庫県 | 猪名川町 | スポーツクラブ21いながわ |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21いなの |
| 兵庫県 | 稲美町 | スポーツクラブ21いなみ |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21うえがはら |
| 兵庫県 | 洲本市 | スポーツクラブ21うしお |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21えびす |
| 兵庫県 | 朝来市 | スポーツクラブ21おおくら |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21おおじ |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21おおしお |
| 兵庫県 | 養父市 | スポーツクラブ21おおたに |
| 兵庫県 | 新温泉町 | スポーツクラブ21おおば |
| 兵庫県 | 小野市 | スポーツクラブ21おおべ |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21おおまち |
| 兵庫県 | 養父市 | スポーツクラブ21おおや |
| 兵庫県 | 神河町 | スポーツクラブ21おおやま |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21おおやま |
| 兵庫県 | 小野市 | スポーツクラブ21オール下東条 |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21おかの |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21おぎの |
| 兵庫県 | 朝来市 | スポーツクラブ21おくがなや |
| 兵庫県 | 香美町 | スポーツクラブ21おくさづ |
| 兵庫県 | 赤穂市 | スポーツクラブ21おさき |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21おさき |
| 兵庫県 | 神河町 | スポーツクラブ21おちだに |
| 兵庫県 | 小野市 | スポーツクラブ21おの「ESPO」 |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21おのころ |
| 兵庫県 | 小野市 | スポーツクラブ21おのひがし |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21かくらい |
| 兵庫県 | 香美町 | スポーツクラブ21かすみ |
| 兵庫県 | 神河町 | スポーツクラブ21かみおだ |
| 兵庫県 | 加東市 | スポーツクラブ21かもがわ |
| 兵庫県 | 小野市 | スポーツクラブ21かわい |
| 兵庫県 | 神河町 | スポーツクラブ21かわかみ |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21かんべ |
| 兵庫県 | 小野市 | スポーツクラブ21きすみの |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21きよたき |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21くげ |
| 兵庫県 | 西脇市 | スポーツクラブ21くすがおか |
| 兵庫県 | 新温泉町 | スポーツクラブ21くとだに |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21くましろ |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21くもべ |
| 兵庫県 | 川西市 | スポーツクラブ21グリーンハイツ |
| 兵庫県 | 川西市 | スポーツクラブ21けやき坂 |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21けやき台 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21こうろ |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21こくふ |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21こまつ |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21こやの里 |
| 兵庫県 | 洲本市 | スポーツクラブ21さかい |
| 兵庫県 | 川西市 | スポーツクラブ21さくら |
| 兵庫県 | 西脇市 | スポーツクラブ21さくら |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21ささはら |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21ささやま |
| 兵庫県 | 香美町 | スポーツクラブ21さつ |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21さの |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21しおた |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21しかま |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21しごう |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21しち |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21しづき |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21しとおり |
| 兵庫県 | 香美町 | スポーツクラブ21しばやま |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21しぼ |
| 兵庫県 | 猪名川町 | スポーツクラブ21しろがね |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21すえなり |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21すがの |
| 兵庫県 | 多可町 | スポーツクラブ21すぎはら |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21すずかけ台 |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21すずはら |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21すみれが丘 |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21せいしゅう |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21そめごうち |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21たかはし |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21たかはま |
| 兵庫県 | 加東市 | スポーツクラブ21たきの |
| 兵庫県 | 養父市 | スポーツクラブ21たきのや |
| 兵庫県 | 朝来市 | スポーツクラブ21たけだ |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21たけだ |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21たにそと |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21ちくさ |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21つい |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21つたさわ |
| 兵庫県 | 猪名川町 | スポーツクラブ21つつじ |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21つつじが丘 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21つと |
| 兵庫県 | 養父市 | スポーツクラブ21であい |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21てらさか |
| 兵庫県 | 神河町 | スポーツクラブ21てらまえ |
| 兵庫県 | 朝来市 | スポーツクラブ21とが |
| 兵庫県 | 朝来市 | スポーツクラブ21とちはら |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21とはら |
| 兵庫県 | 加西市 | スポーツクラブ21とみあい |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21とよおか五荘クラブ |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21とよおか港西クラブ |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21とよおか港東クラブ |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21とよおか三江クラブ |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21とよおか新田クラブ |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21とよおか神美クラブ |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21とよおか中筋クラブ |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21とよおか田鶴野クラブ |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21とよおか奈佐クラブ |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21とよおか八条クラブ |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21とよおか豊岡クラブ |
| 兵庫県 | 洲本市 | スポーツクラブ21とりかい |
| 兵庫県 | 香美町 | スポーツクラブ21ながい |
| 兵庫県 | 高砂市 | スポーツクラブ21なかすじ |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21なかだ |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21なかでら |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21なじお |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21なまぜ |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21なりあい |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21にしき |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21にしき |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21はが |
| 兵庫県 | 神河町 | スポーツクラブ21はせ |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21はなさと |
| 兵庫県 | 多可町 | スポーツクラブ21はななみ |
| 兵庫県 | 新温泉町 | スポーツクラブ21はまさか |
| 兵庫県 | 赤穂市 | スポーツクラブ21はら |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21はんせ |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21ひおき |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21ひがし |
| 兵庫県 | 川西市 | スポーツクラブ21ひがしたに |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21ひじま |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21ひだか |
| 兵庫県 | 香美町 | スポーツクラブ21ひょうご小代 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21ひらき |
| 兵庫県 | 洲本市 | スポーツクラブ21ひろいし |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21ひろた |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21ひろた |
| 兵庫県 | 養父市 | スポーツクラブ21ひろたに |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21ふくすみ |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21ふくすみ |
| 兵庫県 | 加東市 | スポーツクラブ21ふくだ |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21ふなき |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21ふなつ |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21ふるいち |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21ぼうぜ |
| 兵庫県 | 多可町 | スポーツクラブ21まつい |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21まつほ |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21みかた |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21みかた |
| 兵庫県 | 加東市 | スポーツクラブ21みくさ |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21みくにの |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21みずかみ |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21みずほ |
| 兵庫県 | 養父市 | スポーツクラブ21みたに |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21みつ |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21みどり |
| 兵庫県 | 三木市 | スポーツクラブ21みなぎ台 |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21みなと |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21みなみ |
| 兵庫県 | 神河町 | スポーツクラブ21みなみおだ |
| 兵庫県 | 香美町 | スポーツクラブ21むらおか |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21むらくも |
| 兵庫県 | 新温泉町 | スポーツクラブ21もろよせ |
| 兵庫県 | 加東市 | スポーツクラブ21やしろ |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21やしろ |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21やすむろ |
| 兵庫県 | 猪名川町 | スポーツクラブ21やないづ |
| 兵庫県 | 朝来市 | スポーツクラブ21やなせ |
| 兵庫県 | 養父市 | スポーツクラブ21やぶ |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21やまさき |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21やまだ |
| 兵庫県 | 多可町 | スポーツクラブ21やまと |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21やまのうち |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21やわた |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21ゆずり葉 |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21ゆりのき台 |
| 兵庫県 | 加東市 | スポーツクラブ21よねだ |
| 兵庫県 | 朝来市 | スポーツクラブ21よふど |
| 兵庫県 | 相生市 | スポーツクラブ21わかさの |
| 兵庫県 | 猪名川町 | スポーツクラブ21阿古谷 |
| 兵庫県 | 高砂市 | スポーツクラブ21阿弥陀 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21旭陽 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21芦田 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21安井 |
| 兵庫県 | 洲本市 | スポーツクラブ21安乎 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21安室東 |
| 兵庫県 | 上郡町 | スポーツクラブ21鞍居 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21伊勢 |
| 兵庫県 | 高砂市 | スポーツクラブ21伊保 |
| 兵庫県 | 高砂市 | スポーツクラブ21伊保南 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21育波 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21一小校区 |
| 兵庫県 | 加西市 | スポーツクラブ21宇仁 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21浦 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21浦風 |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21越部 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21園田 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21園田東 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21園田南 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21園田北 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21園和 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21園和北 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21遠阪 |
| 兵庫県 | 赤穂市 | スポーツクラブ21塩屋 |
| 兵庫県 | 新温泉町 | スポーツクラブ21奥八田 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21王子 |
| 兵庫県 | 新温泉町 | スポーツクラブ21温泉 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21下坂部 |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21下三方 |
| 兵庫県 | 加西市 | スポーツクラブ21下里 |
| 兵庫県 | 川西市 | スポーツクラブ21加茂 |
| 兵庫県 | 洲本市 | スポーツクラブ21加茂 |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21河東 |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21河内 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21花園 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21花田 |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21賀集 |
| 兵庫県 | 加西市 | スポーツクラブ21賀茂 |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21学園 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21学習 |
| 兵庫県 | 多可町 | スポーツクラブ21笠形 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21釜口 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21瓦林 |
| 兵庫県 | 市川町 | スポーツクラブ21甘地 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21丸橋 |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21丸山 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21貴崎 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21吉見 |
| 兵庫県 | 佐用町 | スポーツクラブ21久崎 |
| 兵庫県 | 川西市 | スポーツクラブ21久代 |
| 兵庫県 | 芦屋市 | スポーツクラブ21宮川 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21魚住 |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21狭間 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21錦が丘 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21錦浦 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21金楽寺 |
| 兵庫県 | 加西市 | スポーツクラブ21九会 |
| 兵庫県 | 養父市 | スポーツクラブ21熊次 |
| 兵庫県 | 新温泉町 | スポーツクラブ21熊谷 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21郡家 |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | スポーツクラブ21月が丘クラブ |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21古知 |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21後川 |
| 兵庫県 | 新温泉町 | スポーツクラブ21御火浦 |
| 兵庫県 | 赤穂市 | スポーツクラブ21御崎 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21光明 |
| 兵庫県 | 三木市 | スポーツクラブ21口吉川(TRY!) |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21広畑 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21広畑第二 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21広峰 |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21広野 |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21弘道 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21杭瀬 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21江井 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21江井島 |
| 兵庫県 | 佐用町 | スポーツクラブ21江川 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21甲子園浜 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21甲東 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21甲陽園 |
| 兵庫県 | 高砂市 | スポーツクラブ21荒井 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21荒川 |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21香島 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21香櫨園 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21香呂みなみ |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21高岡 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21高岡西 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21高丘西 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21高丘東 |
| 兵庫県 | 高砂市 | スポーツクラブ21高砂 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21高小 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21高須 |
| 兵庫県 | 上郡町 | スポーツクラブ21高田 |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21高平 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21高木 |
| 兵庫県 | 赤穂市 | スポーツクラブ21高雄 |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21鴻池 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21黒井 |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21今田 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21佐治 |
| 兵庫県 | 佐用町 | スポーツクラブ21佐用 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21妻鹿 |
| 兵庫県 | 三木市 | スポーツクラブ21細川 |
| 兵庫県 | 赤穂市 | スポーツクラブ21坂越 |
| 兵庫県 | 神河町 | スポーツクラブ21作新 |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21桜台 |
| 兵庫県 | 佐用町 | スポーツクラブ21三河 |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21三田 |
| 兵庫県 | 佐用町 | スポーツクラブ21三日月 |
| 兵庫県 | 三木市 | スポーツクラブ21三木西 |
| 兵庫県 | 三木市 | スポーツクラブ21三木青山 |
| 兵庫県 | 三木市 | スポーツクラブ21三木東 |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21三輪 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21山手 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21山手台 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21山田 |
| 兵庫県 | 上郡町 | スポーツクラブ21山野里 |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21志手原 |
| 兵庫県 | 三木市 | スポーツクラブ21志染(夢スポ) |
| 兵庫県 | 三木市 | スポーツクラブ21自由が丘西(スマイル) |
| 兵庫県 | 三木市 | スポーツクラブ21自由が丘東(コスモ) |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21七松 |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21室津 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21室津 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21若葉 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21手柄 |
| 兵庫県 | 洲本市 | スポーツクラブ21洲本第三 |
| 兵庫県 | 洲本市 | スポーツクラブ21洲本第二 |
| 兵庫県 | 西脇市 | スポーツクラブ21重春・野村 |
| 兵庫県 | 養父市 | スポーツクラブ21宿南 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21春日部 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21春風 |
| 兵庫県 | 新温泉町 | スポーツクラブ21春来 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21勝原 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21小園 |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21小坂 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21小川 |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21小宅 |
| 兵庫県 | 市川町 | スポーツクラブ21小畑 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21小浜 |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21小野 |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21小野 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21松が丘 |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21松ヶ丘 |
| 兵庫県 | 猪名川町 | スポーツクラブ21松尾台 |
| 兵庫県 | 新温泉町 | スポーツクラブ21照来 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21上ヶ原南 |
| 兵庫県 | 三木市 | スポーツクラブ21上吉川 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21上久下 |
| 兵庫県 | 上郡町 | スポーツクラブ21上郡 |
| 兵庫県 | 佐用町 | スポーツクラブ21上月 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21上甲子園 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21上坂部 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21上菅 |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21城下 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21城乾 |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21城崎 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21城西 |
| 兵庫県 | 赤穂市 | スポーツクラブ21城西 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21城巽 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21城東 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21城南 |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21城南 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21城北 |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21城北 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21城陽 |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21新宮 |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21神岡 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21神楽 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21神原 |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21神津 |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21神部 |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21神野 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21進修 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21人丸 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21仁井 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21仁川 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21水堂 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21崇広 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21菅生 |
| 兵庫県 | 市川町 | スポーツクラブ21瀬加 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21成徳 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21成文 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21清水 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21清和 |
| 兵庫県 | 川西市 | スポーツクラブ21清和台 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21生田 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21生穂 |
| 兵庫県 | 芦屋市 | スポーツクラブ21精道 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21西 |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21西紀南 |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21西紀北 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21西宮浜 |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21西栗栖 |
| 兵庫県 | 加西市 | スポーツクラブ21西在田 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21西山 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21西谷 |
| 兵庫県 | 養父市 | スポーツクラブ21西谷 |
| 兵庫県 | 西脇市 | スポーツクラブ21西脇・津万 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21青山 |
| 兵庫県 | 太子町 | スポーツクラブ21石海 |
| 兵庫県 | 新温泉町 | スポーツクラブ21赤崎 |
| 兵庫県 | 上郡町 | スポーツクラブ21赤松 |
| 兵庫県 | 赤穂市 | スポーツクラブ21赤穂 |
| 兵庫県 | 赤穂市 | スポーツクラブ21赤穂西 |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21摂陽 |
| 兵庫県 | 川西市 | スポーツクラブ21川西(やなぎクラブ) |
| 兵庫県 | 川西市 | スポーツクラブ21川西北(かわきたクラブ) |
| 兵庫県 | 市川町 | スポーツクラブ21川辺 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21浅野 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21船坂 |
| 兵庫県 | 上郡町 | スポーツクラブ21船坂 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21船場 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21前山 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21前之庄 |
| 兵庫県 | 高砂市 | スポーツクラブ21曽根 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21曽左 |
| 兵庫県 | 西脇市 | スポーツクラブ21双葉 |
| 兵庫県 | 相生市 | スポーツクラブ21双葉 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21増位 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21多賀 |
| 兵庫県 | 川西市 | スポーツクラブ21多田 |
| 兵庫県 | 川西市 | スポーツクラブ21多田東 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21太市 |
| 兵庫県 | 太子町 | スポーツクラブ21太田 |
| 兵庫県 | 芦屋市 | スポーツクラブ21打出浜 |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21大芋 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21大観 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21大久保 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21大久保南 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21大社 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21大庄 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21大津 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21大津茂 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21大島 |
| 兵庫県 | 猪名川町 | スポーツクラブ21大島 |
| 兵庫県 | 洲本市 | スポーツクラブ21大野 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21沢池 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21谷内 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21谷八木 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21段上 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21段上西 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21置塩 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21竹谷 |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21竹野 |
| 兵庫県 | 佐用町 | スポーツクラブ21中安 |
| 兵庫県 | 相生市 | スポーツクラブ21中央 |
| 兵庫県 | 三木市 | スポーツクラブ21中吉川 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21中崎 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21中山五月台 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21中山桜台 |
| 兵庫県 | 洲本市 | スポーツクラブ21中川原 |
| 兵庫県 | 豊岡市 | スポーツクラブ21中竹野 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21朝霧 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21潮 |
| 兵庫県 | 芦屋市 | スポーツクラブ21潮見 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21長洲 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21長沢 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21長尾 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21長尾台 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21長尾南 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21鳥羽 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21津田 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21塚口 |
| 兵庫県 | 市川町 | スポーツクラブ21鶴居 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21的形 |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21天神川 |
| 兵庫県 | 香美町 | スポーツクラブ21兎塚 |
| 兵庫県 | 洲本市 | スポーツクラブ21都志 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21砥堀 |
| 兵庫県 | 三木市 | スポーツクラブ21東吉川(ひがし) |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21東栗栖 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21東山台 |
| 兵庫県 | 加東市 | スポーツクラブ21東条 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21藤江 |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21道谷 |
| 兵庫県 | 佐用町 | スポーツクラブ21徳久 |
| 兵庫県 | 相生市 | スポーツクラブ21那波 |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | スポーツクラブ21灘ゆづるは |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21南大津 |
| 兵庫県 | 養父市 | スポーツクラブ21南谷 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21難波 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21二見 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21二見西 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21二見北 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21尼崎北 |
| 兵庫県 | 加西市 | スポーツクラブ21日吉 |
| 兵庫県 | 西脇市 | スポーツクラブ21日野 |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21播磨高原東 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21梅香 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21売布 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21白鳥 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21白浜 |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21畑 |
| 兵庫県 | 養父市 | スポーツクラブ21八鹿 |
| 兵庫県 | 丹波篠山市 | スポーツクラブ21八上 |
| 兵庫県 | 新温泉町 | スポーツクラブ21八田 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21八木 |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21半田 |
| 兵庫県 | 太子町 | スポーツクラブ21斑鳩 |
| 兵庫県 | 西脇市 | スポーツクラブ21比也野 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21美座 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21美和 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21氷上西 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21氷上中央 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21氷上東 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21氷上南 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21氷上北 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21浜 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21浜田 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21浜脇 |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21富士 |
| 兵庫県 | 加西市 | スポーツクラブ21富田 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21富島 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21武庫 |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21武庫 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21武庫の里 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21武庫庄 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21武庫東 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21武庫南 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21武庫北 |
| 兵庫県 | 高砂市 | スポーツクラブ21米田 |
| 兵庫県 | 高砂市 | スポーツクラブ21米田西 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21別所 |
| 兵庫県 | 三木市 | スポーツクラブ21別所(MOE) |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21母子 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21宝塚 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21峰相 |
| 兵庫県 | 西脇市 | スポーツクラブ21芳田 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21北夙川 |
| 兵庫県 | 加西市 | スポーツクラブ21北条 |
| 兵庫県 | 加西市 | スポーツクラブ21北条東 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21北難波 |
| 兵庫県 | 高砂市 | スポーツクラブ21北浜 |
| 兵庫県 | 川西市 | スポーツクラブ21北陵 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21北六甲台 |
| 兵庫県 | 川西市 | スポーツクラブ21牧の台 |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21本庄 |
| 兵庫県 | 佐用町 | スポーツクラブ21幕山 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21末広 |
| 兵庫県 | 多可町 | スポーツクラブ21妙見 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21名和 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21明城 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21明石 |
| 兵庫県 | 川西市 | スポーツクラブ21明峰 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21鳴尾 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21鳴尾東 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21鳴尾北 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21網干 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21網干西 |
| 兵庫県 | 宍粟市 | スポーツクラブ21野原 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21野島 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21野里 |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21弥生 |
| 兵庫県 | 相生市 | スポーツクラブ21矢野 |
| 兵庫県 | 淡路市 | スポーツクラブ21柳沢 |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21揖西西 |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21揖西東 |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21揖保 |
| 兵庫県 | 伊丹市 | スポーツクラブ21有岡 |
| 兵庫県 | 赤穂市 | スポーツクラブ21有年 |
| 兵庫県 | 洲本市 | スポーツクラブ21由良 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21余部 |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21誉田 |
| 兵庫県 | 西宮市 | スポーツクラブ21用海 |
| 兵庫県 | 三田市 | スポーツクラブ21藍 |
| 兵庫県 | 佐用町 | スポーツクラブ21利神 |
| 兵庫県 | 上郡町 | スポーツクラブ21梨ヶ原 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21立花 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21立花西 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21立花南 |
| 兵庫県 | 尼崎市 | スポーツクラブ21立花北 |
| 兵庫県 | 太子町 | スポーツクラブ21龍田 |
| 兵庫県 | たつの市 | スポーツクラブ21龍野 |
| 兵庫県 | 宝塚市 | スポーツクラブ21良元 |
| 兵庫県 | 三木市 | スポーツクラブ21緑が丘(With) |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21林 |
| 兵庫県 | 姫路市 | スポーツクラブ21林田 |
| 兵庫県 | 明石市 | スポーツクラブ21和坂 |
| 兵庫県 | 丹波市 | スポーツクラブ21和田 |
| 兵庫県 | 朝来市 | スポーツクラブ21和田山 |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | すぽーつくらぶありの |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | スポーツクラブおおぞう・光・みらい |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | スポーツクラブにしまいこ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | スポーツクラブ道場 |
| 兵庫県 | 福崎町 | スポーツネットワークUS |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | スポーツパーク舞子 |
| 兵庫県 | 神戸市(兵庫区) | スポーツ倶楽部めいしん |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | だいちスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 福崎町 | たかおかスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | たかくらだいスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | つつじが丘スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | であいスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(東灘区) | ナイス本一クラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(長田区) | ながたスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(灘区) | にしごうスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(東灘区) | のびのび魚崎クラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(中央区) | はっと!なぎさクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | はなやまスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(東灘区) | ひがしなだクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | ひよどり台元気クラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(東灘区) | みかきた上の山クラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(東灘区) | みかげスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(長田区) | みくらスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(中央区) | みなとスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(灘区) | みのおかクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | みのたにスポーツ交流クラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | ミラクルはなたにクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(東灘区) | もとみなスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 西宮市 | やまぐちスポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(中央区) | レッツこうべスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | 阿万スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 姫路市 | 安富南スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 姫路市 | 安富北スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 養父市 | 伊佐地区スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 伊川谷スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(東灘区) | 渦が森あいあいクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(中央区) | 雲中ウイングクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | 塩屋あらかしクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | 塩屋北スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 押部谷スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | 横尾スポーツひろば |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | 乙木スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | 下畑台やまももクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(兵庫区) | 会下山 WaiWai クラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 学園グリーンスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 樫野台スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 西宮市 | 瓦木スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(長田区) | 丸山ひばりスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 芦屋市 | 岩園スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 岩岡スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(長田区) | 宮川もりもりクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(中央区) | 宮本スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 玉一小スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(長田区) | 駒ヶ林スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 君影スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 桂木きらきらスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(長田区) | 五位の池スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 養父市 | 口大屋スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(東灘区) | 向洋スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 好徳スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 広陵スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(中央区) | 港島スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 甲緑あじさいスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(灘区) | 高羽スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | 高丸総合クラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 高津橋スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 養父市 | 高柳地区スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 高和スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 西宮市 | 今津スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 桜が丘のびのびスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 桜の宮さわやかクラブ |
| 兵庫県 | 芦屋市 | 三条スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(中央区) | 山の手カリヨンスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 山田地域スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 枝吉げんきクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 鹿の子台スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(長田区) | 室っ子スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | 若宮のりのりクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | 若草スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 狩場さわやかスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(東灘区) | 住吉スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 西宮市 | 夙川スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 春日台スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(中央区) | 春日野スプリングクラブ |
| 兵庫県 | 養父市 | 小佐スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | 小束山スマイルクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 小部っ子スポーツアートクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 小部東ほっとスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | 松尾ふぁみりぃクラブ |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | 沼島スポーツクラブ21おのころ |
| 兵庫県 | 神戸市(中央区) | 上筒井サンサンクラブ |
| 兵庫県 | 西宮市 | 深津スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(長田区) | 真野スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(長田区) | 真陽ひまわりクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | 神の谷ぷらっとスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 神出スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | 神陵台キラキラスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | 垂水アンカークラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(兵庫区) | 水木スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | 菅の台シーズスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(灘区) | 成徳スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 星和台スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 西山スマイルクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | 西須磨はつらつスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(灘区) | 西灘わくわくスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | 西落合レインボークラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | 千代が丘ゆめクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | 千鳥きらめきクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 泉台ふれあいスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | 多井畑スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | 多聞の丘スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | 多聞台わくわくスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | 多聞東スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 太山寺けやきスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 谷上ゆうゆうクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 淡河スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(長田区) | 池田かがやきスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 豊岡市 | 竹野南スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 筑紫が丘スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(中央区) | 中央スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 芦屋市 | 朝日ケ丘スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 南あわじ市 | 潮美台スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 長坂なでしこスポーツ広場 |
| 兵庫県 | 神戸市(長田区) | 長田南スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 長尾スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(灘区) | 鶴甲ふれあいクラブ |
| 兵庫県 | 福崎町 | 田原スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | 東スマイルクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | 東垂水スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | 東舞子スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | 東落合スポーツクラブ新・ごんたろう姫の会 |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 藤原台フレンドリークラブ |
| 兵庫県 | 芦屋市 | 特定非営利活動法人 アスロン |
| 兵庫県 | 神戸市(灘区) | 灘せせらぎクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 南五葉いきいきスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 西宮市 | 南甲子園スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | 南落合フレンドリークラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | 白川クラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 櫨谷スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 福崎町 | 八千種スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 八多ふれあいクラブ |
| 兵庫県 | 西宮市 | 樋ノ口スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 美賀多台スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(灘区) | 稗田わくわくクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(兵庫区) | 浜山Can成る倶楽部 |
| 兵庫県 | 芦屋市 | 浜風スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(灘区) | 福住クラブウィズ |
| 兵庫県 | 神戸市(東灘区) | 福池文化・スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(兵庫区) | 兵庫大開さわやかスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 平野あたごスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 姫路市 | 豊富スポーツクラブ21 |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 北五葉クラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 北山GOGOスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | 北須磨スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(東灘区) | 本三クラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(東灘区) | 本庄五輪クラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(東灘区) | 本二のびのびスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(灘区) | 摩耶スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | 妙法寺グリーンスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(兵庫区) | 夢野の丘スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(長田区) | 名倉スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(垂水区) | 名谷くすのきSUNクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 木津スポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 有瀬ふれあいスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(北区) | 有馬わくわくクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(須磨区) | 竜が台ふれあいクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(長田区) | 蓮池すこやかクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(東灘区) | 六甲アイランドスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(灘区) | 六甲すこやかクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(灘区) | 六甲山のふれあいスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(兵庫区) | 和田岬はちのすスポーツクラブ |
| 兵庫県 | 神戸市(西区) | 糀台スポーツクラブ |
| 和歌山県 | かつらぎ町 | NPO法人憩楽クラブかつらぎ |
| 和歌山県 | すさみ町 | すさみ町総合型地域スポーツクラブ検討委員会 |
| 和歌山県 | みなべ町 | みなべ町梅の里スポーツクラブ設立準備委員会 |
| 和歌山県 | 海南市 | NPO法人下津スポーツクラブ |
| 和歌山県 | 海南市 | NPO法人ゆうゆうスポーツクラブ海南 |
| 和歌山県 | 海南市 | NPO法人スポーツ・リパブリック ソラティオーラ和歌山 |
| 和歌山県 | 岩出市 | NPO法人岩出FCアズール |
| 和歌山県 | 岩出市 | NPO法人サン・スマイルいわで |
| 和歌山県 | 岩出市 | NPO法人岩出まなびくらぶ |
| 和歌山県 | 紀の川市 | 桃山体育王国スポーツクラブ |
| 和歌山県 | 紀の川市 | あったかクラブ |
| 和歌山県 | 紀美野町 | 紀美野町総合型地域クラブ検討委員会 |
| 和歌山県 | 橋本市 | NPO法人げんき倶楽部はしもと |
| 和歌山県 | 橋本市 | 初橋スポーツクラブ設立準備委員会 |
| 和歌山県 | 橋本市 | 一般社団法人ファインクラブ高野口 |
| 和歌山県 | 九度山町 | (仮称)九度山町総合型クラブ検討委員会 |
| 和歌山県 | 串本町 | 潮岬おもしろスポーツクラブ |
| 和歌山県 | 古座川町 | 古座川筋力トレーニングクラブ |
| 和歌山県 | 御坊市 | 御坊スポーツクラブ |
| 和歌山県 | 御坊市 | GOBOクラブ |
| 和歌山県 | 御坊市 | みらい |
| 和歌山県 | 広川町 | 広川町総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会 |
| 和歌山県 | 広川町 | 津木総合型クラブ |
| 和歌山県 | 高野町 | (仮称)高野町スポーツクラブ |
| 和歌山県 | 上富田町 | NPO法人くちくまのクラブ |
| 和歌山県 | 新宮市 | 元気クラブしんぐう |
| 和歌山県 | 太地町 | (仮称)太地町総合型クラブ検討委員会 |
| 和歌山県 | 田辺市 | NPO法人会津スポーツクラブ |
| 和歌山県 | 田辺市 | ESスポーツクラブ |
| 和歌山県 | 田辺市 | 龍神スポーツクラブ |
| 和歌山県 | 田辺市 | 熊野本宮スポーツクラブ |
| 和歌山県 | 湯浅町 | 湯浅総合型地域スポーツクラブ |
| 和歌山県 | 日高川町 | 南山スポーツクラブ |
| 和歌山県 | 日高町 | NPO法人日高総合型クラブ |
| 和歌山県 | 白浜町 | しらはま温泉スポーツクラブ |
| 和歌山県 | 有田市 | スポーツクラブありだ |
| 和歌山県 | 有田市 | 港スポーツクラブ |
| 和歌山県 | 有田市 | ACT ASSIST ARIDA |
| 和歌山県 | 有田市 | NPO法人和歌山箕島球友会 |
| 和歌山県 | 有田川町 | 総合型地域スポーツクラブ有田川 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 紀の国アスリートクラブ |
| 和歌山県 | 和歌山市 | わひがしスポーツクラブ(仮称) |
| 和歌山県 | 和歌山市 | NPO法人和歌山セーリングクラブ |
| 和歌山県 | 和歌山市 | NPO法人スポーツクラブ和歌山ヴィーヴォ |
| 和歌山県 | 和歌山市 | NPO法人スポーツチャンネル |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 安原スポーツクラブ |
| 和歌山県 | 和歌山市 | NPO法人紀三井寺スポーツクラブ |
| 和歌山県 | 和歌山市 | スプラウトスポーツクラブ和歌山 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | wadaiクラブ(仮)設立準備委員会 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 和北総合型クラブ |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 総合型地域スポーツクラブ壁ん原人 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山さわやかスポーツクラブ設立準備委員会 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 総合型クラブ まこと会 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 総合型クラブ TELAKOYA |
| 和歌山県 | 和歌山市 | NPO法人総合型地域スポーツクラブBBS21 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | アルテリーヴォ和歌山 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 和歌山市中心市街地スポーツクラブ設立準備委員会 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | セレッソスポーツクラブ和歌山 |
| 鳥取県 | 岩美町 | 岩美総合型地域スポーツクラブ |
| 鳥取県 | 境港市 | NPO法人ウルトラスポーツクラブ |
| 鳥取県 | 境港市 | 境スポーツクラブ |
| 鳥取県 | 江府町 | 奥大山ぶなの森クラブ |
| 鳥取県 | 若桜町 | 若桜クラブ |
| 鳥取県 | 倉吉市 | NPO法人かほくスポーツクラブ |
| 鳥取県 | 倉吉市 | サンリンク・スポーツ |
| 鳥取県 | 大山町 | スポーツしょい大山 |
| 鳥取県 | 智頭町 | スポねっとちづ |
| 鳥取県 | 鳥取市 | NPO法人鳥取スポーツクラブ |
| 鳥取県 | 鳥取市 | けたかスポーツクラブ |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 青谷スポーツクラブ |
| 鳥取県 | 鳥取市 | NPO法人鹿の助スポーツクラブ |
| 鳥取県 | 鳥取市 | NPO法人地域スポーツ推進協会 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 「国府クラブ」総合型地域スポーツクラブ |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 一般社団法人 すなばスポーツ |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 琴の浦クラブ |
| 鳥取県 | 南部町 | NPO法人南部町総合型地域スポーツクラブ スポnetなんぶ |
| 鳥取県 | 日南町 | にちなんスポーツクラブ |
| 鳥取県 | 日野町 | Do.スポーツ |
| 鳥取県 | 伯耆町 | 一般社団法人 ほうきスマイリースポーツクラブ |
| 鳥取県 | 米子市 | NPO法人やまつみスポーツクラブ |
| 鳥取県 | 米子市 | あすなろスポーツクラブ |
| 鳥取県 | 米子市 | あいだクラブ |
| 鳥取県 | 北栄町 | 一般財団法人 北栄スポーツクラブ |
| 岡山県 | 井原市 | いばら生き生きクラブ |
| 岡山県 | 岡山市 | 藤田総合スポーツクラブ |
| 岡山県 | 岡山市 | 富山スポーツクラブ |
| 岡山県 | 岡山市 | NPO法人桃太郎夢クラブ |
| 岡山県 | 岡山市 | 瀬戸スポーツクラブ |
| 岡山県 | 岡山市 | きらり☆スポーツクラブ |
| 岡山県 | 岡山市 | 二藤スポーツクラブ |
| 岡山県 | 岡山市 | YNM香和スポーツクラブ |
| 岡山県 | 笠岡市 | 笠岡総合スポーツクラブ |
| 岡山県 | 笠岡市 | NPO法人おかやまスポーツクラブ虹 |
| 岡山県 | 鏡野町 | かがみのスポーツクラブ |
| 岡山県 | 玉野市 | 玉野市総合スポーツクラブ |
| 岡山県 | 玉野市 | みやまスポーツクラブ |
| 岡山県 | 高梁市 | 高梁コミュニティ スポーツクラブ ピオーネ |
| 岡山県 | 勝央町 | NPO法人勝央町健康スポーツクラブ |
| 岡山県 | 新見市 | 総合スポーツクラブ新見 |
| 岡山県 | 真庭市 | スポーツ・レクリエーション 倶楽部くせ |
| 岡山県 | 真庭市 | しらうめスポーツクラブ |
| 岡山県 | 瀬戸内市 | ゆめりくクラブ |
| 岡山県 | 赤磐市 | NPO法人吉井スポレククラブ |
| 岡山県 | 赤磐市 | 一般社団法人ELSOL |
| 岡山県 | 浅口市 | NPO法人あさくちスポーツクラブ遊ぶところ |
| 岡山県 | 倉敷市 | 児島マリンスポーツクラブ |
| 岡山県 | 早島町 | 早島町総合型地域スポーツクラブ(設立準備中) |
| 岡山県 | 総社市 | きよねスポーツくらぶ |
| 岡山県 | 津山市 | しょうぼくスポーツクラブ |
| 岡山県 | 備前市 | びぜん優くらぶ |
| 岡山県 | 美咲町 | NPO法人美咲町柵原星の里スポレク倶楽部 |
| 岡山県 | 美咲町 | 夢咲クラブ |
| 岡山県 | 美作市 | 美作市粟井スポーツ振興会 |
| 岡山県 | 矢掛町 | NPO法人やかげスポーツクラブ |
| 岡山県 | 和気町 | 総合型スポーツ和気クラブ |
| 島根県 | 安来市 | NPO法人さくら総合スポーツクラブ |
| 島根県 | 安来市 | みなみ総合スポーツクラブ |
| 島根県 | 安来市 | 島田総合スポーツクラブ |
| 島根県 | 雲南市 | NPO法人Yu-Gaku加茂スポーツクラブ |
| 島根県 | 雲南市 | 大東町総合型スポーツクラブ |
| 島根県 | 雲南市 | みとやスポーツクラブ |
| 島根県 | 益田市 | NPO法人ボアソルテスポーツクラブ |
| 島根県 | 益田市 | Pegasusクラブ |
| 島根県 | 奥出雲町 | 奥出雲スポーツクラブ |
| 島根県 | 出雲市 | いずもスポーツクラブ21 |
| 島根県 | 出雲市 | はまやまスポーツクラブ |
| 島根県 | 出雲市 | 出雲ファーストクラブ |
| 島根県 | 出雲市 | センタースポーツクラブ |
| 島根県 | 出雲市 | ゆうゆうきたクラブ |
| 島根県 | 出雲市 | NPO法人リバーサイドスポーツクラブ |
| 島根県 | 出雲市 | スポーツクラブおろち |
| 島根県 | 出雲市 | NPO法人斐川体育協会 ひかわスポーツ夢クラブ |
| 島根県 | 出雲市 | スポーツクラブ多伎 |
| 島根県 | 松江市 | NPO法人しんじ湖スポーツクラブ |
| 島根県 | 松江市 | 竹矢スポーツクラブ |
| 島根県 | 松江市 | 美保関クラブ |
| 島根県 | 松江市 | おおの輪・和・ワークラブ |
| 島根県 | 松江市 | 城北総合スポーツクラブ |
| 島根県 | 松江市 | NPO法人SPORTIVOひがしいずも |
| 島根県 | 川本町 | かわもとスポーツクラブ |
| 島根県 | 大田市 | 銀ギンginスポーツクラブ |
| 島根県 | 津和野町 | 小川地区体育連盟 |
| 島根県 | 飯南町 | いいなんスポーツクラブ |
| 島根県 | 浜田市 | 煌めきクラブ周布 |
| 島根県 | 浜田市 | NPO法人かなぎアスレチックきんた |
| 島根県 | 浜田市 | あさひスポーツクラブ |
| 島根県 | 浜田市 | みすみスポーツクラブ |
| 島根県 | 浜田市 | NPO法人浜田フットサルクラブ |
| 広島県 | 安芸高田市 | みつやの里スポーツクラブ |
| 広島県 | 安芸高田市 | NPO法人いきいきクラブたかみや |
| 広島県 | 安芸太田町 | 安芸太田ファン×Funクラブ |
| 広島県 | 熊野町 | 筆の里スポーツクラブ |
| 広島県 | 呉市 | ふれ愛!!瀬戸内スポーツクラブ |
| 広島県 | 呉市 | 清盛スポーツクラブ |
| 広島県 | 呉市 | きて呉んさいクラブ |
| 広島県 | 広島市 | KoiKoiスポーツクラブ |
| 広島県 | 広島市 | らくらくクラブ |
| 広島県 | 広島市 | 鯉城ふれあいクラブ |
| 広島県 | 広島市 | FEスポーツクラブ |
| 広島県 | 広島市 | 伴地区スポーツクラブ |
| 広島県 | 広島市 | 南観フレッシュクラブ |
| 広島県 | 広島市 | オールラウンドすずはり |
| 広島県 | 江田島市 | NPO法人江田島eスポーツクラブ |
| 広島県 | 三原市 | 沼田川ファミリークラブ |
| 広島県 | 三次市 | NPO法人みわスポーツクラブ |
| 広島県 | 庄原市 | 庄原さくらスポーツクラブ |
| 広島県 | 世羅町 | せらスポーツクラブ |
| 広島県 | 大崎上島町 | わいわいスポーツクラブ |
| 広島県 | 大竹市 | 大竹市総合型地域スポーツクラブ |
| 広島県 | 竹原市 | NPO法人バンブースポーツクラブ |
| 広島県 | 東広島市 | わくわくスポーツランドこうち |
| 広島県 | 廿日市市 | NPO法人廿日市スポーツクラブ |
| 広島県 | 廿日市市 | ユアックさいきスポーツクラブ |
| 広島県 | 廿日市市 | NPO法人妹背ウォーターフォールクラブ |
| 広島県 | 尾道市 | NPO法人しまなみスポーツクラブ |
| 広島県 | 尾道市 | NPO法人フレンド・シップせとだ |
| 広島県 | 府中市 | 協和ふれあいスポーツクラブ |
| 広島県 | 府中町 | 一般社団法人呉娑々宇スポーツクラブ |
| 広島県 | 福山市 | 沼南スポーツクラブ |
| 広島県 | 福山市 | 東部スポーツクラブ |
| 広島県 | 北広島町 | どんぐりクラブ屋台村 |
| 広島県 | 北広島町 | 大朝人くらぶ |
| 広島県 | 北広島町 | よろずや広島北 |
| 広島県 | 北広島町 | 一般社団法人芸北道場 |
| 広島県 | 北広島町 | 千代田総合型地域スポーツクラブ |
| 山口県 | 阿武町 | 宇田ふれあいクラブ |
| 山口県 | 宇部市 | NPO法人コミュニティスポーツくすのき |
| 山口県 | 宇部市 | NPO法人Goppoええぞなクラブ |
| 山口県 | 宇部市 | 特定非営利活動法人おもしろファーム |
| 山口県 | 宇部市 | 白鳥健康教室 |
| 山口県 | 宇部市 | よりあい処 西が丘 |
| 山口県 | 宇部市 | おばやまエンジョイクラブ |
| 山口県 | 下関市 | いきいき健康スポーツ教室 |
| 山口県 | 下関市 | 総合型地域スポーツクラブBLUE ROSE |
| 山口県 | 下関市 | コミュニティクラブ東亜 |
| 山口県 | 下関市 | 一般社団法人菊川スポーツクラブ |
| 山口県 | 下関市 | 川中スポーツ振興会 |
| 山口県 | 下関市 | 王喜スポーツ・コミュニティクラブ |
| 山口県 | 下関市 | 角島地区スポーツ育成クラブ |
| 山口県 | 下関市 | 豊田中いなほ倶楽部 |
| 山口県 | 下関市 | コミスポ夢が丘 |
| 山口県 | 下関市 | NPO法人セイザン下関スポーツクラブ |
| 山口県 | 下松市 | くだまつ絆星スポーツクラブ |
| 山口県 | 岩国市 | 特定非営利活動法人ゆうスポーツクラブ |
| 山口県 | 岩国市 | KUGAスポーツクラブ |
| 山口県 | 岩国市 | IDBスポーツクラブ |
| 山口県 | 岩国市 | 美和スポーツクラブ |
| 山口県 | 岩国市 | ほんごう維新クラブ |
| 山口県 | 岩国市 | 美川スポーツクラブ まめな会 |
| 山口県 | 岩国市 | SHOKOエンジョイ倶楽部 |
| 山口県 | 光市 | スポーツNPO法人ひかりクラブ |
| 山口県 | 山口市 | 鋳銭司蔵六コミュニティスポーツクラブ |
| 山口県 | 山口市 | 佐山コミュニティスポーツクラブ |
| 山口県 | 山口市 | 二島コミュニティクラブ |
| 山口県 | 山口市 | 名田島コミュニティクラブ |
| 山口県 | 山口市 | コミュニティスポーツクラブあとう |
| 山口県 | 山口市 | SSC西京 |
| 山口県 | 山陽小野田市 | 出合いちょうクラブ |
| 山口県 | 山陽小野田市 | すげえちゃ・高泊 |
| 山口県 | 周南市 | 新南陽レクリエーション・スポーツ推進委員会 |
| 山口県 | 周南市 | 鹿野スポーツ振興会 |
| 山口県 | 周南市 | 今宿スポーツクラブ |
| 山口県 | 周南市 | くめくめ倶楽部 |
| 山口県 | 周南市 | 櫛浜スポーツクラブ |
| 山口県 | 周防大島町 | NPO法人ココロとカラダ健究会 |
| 山口県 | 上関町 | かみのせきんドリームズ |
| 山口県 | 長門市 | クラブネッツ大畑 |
| 山口県 | 長門市 | いがみ倶楽部 |
| 山口県 | 長門市 | 俵山スポーツクラブ |
| 山口県 | 長門市 | 長門スポーツクラブ |
| 山口県 | 田布施町 | 田布施スポーツクラブ |
| 山口県 | 田布施町 | コミュニティスポーツ城南 |
| 山口県 | 萩市 | むつみスポーツ振興会 |
| 山口県 | 萩市 | 至誠館クラブ |
| 山口県 | 美祢市 | むぎがわ元気クラブ |
| 山口県 | 平生町 | 平生ゆうゆうクラブ |
| 山口県 | 防府市 | 総合型スポーツクラブ防府 |
| 山口県 | 柳井市 | SAスポーツクラブ |
| 山口県 | 和木町 | 和木町総合型地域スポーツクラブ |
| 香川県 | さぬき市 | あい・クラブ |
| 香川県 | 宇多津町 | 一般社団法人 DISPORT キラキラ うたづ |
| 香川県 | 観音寺市 | 一ノ谷スポーツクラブ |
| 香川県 | 観音寺市 | ちょーほいクラブ |
| 香川県 | 丸亀市 | NPO法人ELF丸亀 |
| 香川県 | 丸亀市 | NPO法人スポーツクラブ飯山 |
| 香川県 | 琴平町 | ヴィスポことひら |
| 香川県 | 琴平町 | 琴平サッカークラブ(エスポワール) |
| 香川県 | 高松市 | NPO法人シーガルスポーツクラブ |
| 香川県 | 高松市 | ふれあい一番地 |
| 香川県 | 高松市 | 香南ししまるスポーツクラブ |
| 香川県 | 高松市 | 屋島UROスポーツクラブ |
| 香川県 | 高松市 | むれスポーツクラブ |
| 香川県 | 高松市 | 弦打スポーツクラブ |
| 香川県 | 高松市 | 栗林スポーツクラブ |
| 香川県 | 高松市 | さらスポーツクラブ |
| 香川県 | 高松市 | 一般社団法人スポルトフェライン高松 |
| 香川県 | 高松市 | NPO法人カマタマーレスポーツクラブ |
| 香川県 | 高松市 | 西高松スポーツクラブ |
| 香川県 | 高松市 | WellnessFam |
| 香川県 | 坂出市 | みんなでスポーツさかいで |
| 香川県 | 三豊市 | 三豊わくわくふれあい倶楽部 |
| 香川県 | 三豊市 | NPO法人オリーブ |
| 香川県 | 三木町 | さぬき三木スポーツクラブ |
| 香川県 | 小豆島町 | オリーブ100 |
| 香川県 | 多度津町 | ジョイナスたどつ |
| 香川県 | 東かがわ市 | しろとりスポーツクラブ |
| 香川県 | 東かがわ市 | ひけたスポーツクラブ |
| 香川県 | 東かがわ市 | とらまるクラブONLY・ONE |
| 徳島県 | つるぎ町 | くらぶつるぎっこ |
| 徳島県 | 阿南市 | Rexなかがわ |
| 徳島県 | 阿南市 | サンアリーナスポーツクラブ |
| 徳島県 | 阿南市 | スポーツクラブ はーぷな長生 |
| 徳島県 | 阿波市 | あわスポーツクラブ |
| 徳島県 | 阿波市 | あわ遊くらぶ |
| 徳島県 | 阿波市 | NPO法人AWAにじいろクラブ |
| 徳島県 | 海陽町 | NPO法人海陽愛あいクラブ |
| 徳島県 | 吉野川市 | 吉野川スポーツクラブ |
| 徳島県 | 吉野川市 | おえっこスポーツクラブ |
| 徳島県 | 佐那河内村 | さなごうちスポーツクラブ |
| 徳島県 | 三好市 | いけだスポーツクラブ |
| 徳島県 | 勝浦町 | 特定非営利活動法人 K-Friends |
| 徳島県 | 小松島市 | NPO法人 みなと小松島スポーツクラブ |
| 徳島県 | 松茂町 | 松茂スポーツクラブ |
| 徳島県 | 上板町 | 上板ふれあいクラブ |
| 徳島県 | 神山町 | 神山町スポーツクラブ |
| 徳島県 | 石井町 | いしいスポーツクラブ |
| 徳島県 | 石井町 | NPO法人 徳島RAPAZスポーツクラブ |
| 徳島県 | 東みよし町 | おおくすクラブ |
| 徳島県 | 徳島市 | NPO法人 徳島スポーツクラブ・カバロス |
| 徳島県 | 徳島市 | えのみや睦会 |
| 徳島県 | 徳島市 | NPO法人 ひょうたん島クラブ |
| 徳島県 | 那賀町 | 那賀よしクラブ |
| 徳島県 | 板野町 | 板野ぴょん太スポーツクラブ |
| 徳島県 | 美波町 | ゆきスポーツクラブ |
| 徳島県 | 美波町 | スポーツネットワークひわさ夢くらぶ |
| 徳島県 | 美馬市 | 特定非営利活動法人 うだつコミュニティースポーツクラブ |
| 徳島県 | 美馬市 | スポーツクラブ美馬 |
| 徳島県 | 美馬市 | あなぶきスポーツクラブ |
| 徳島県 | 美馬市 | AMEMBO |
| 徳島県 | 美馬市 | 木屋平スポーツクラブ |
| 徳島県 | 北島町 | 北島スポーツクラブ |
| 徳島県 | 鳴門市 | 一般社団法人 NICE |
| 徳島県 | 鳴門市 | NARUTO総合型スポーツクラブ |
| 徳島県 | 藍住町 | NPO法人 あいずみスポーツクラブ |
| 愛媛県 | 愛南町 | 南宇和スポーツクラブ |
| 愛媛県 | 伊予市 | 伊予地域総合型郡中スポレククラブ |
| 愛媛県 | 宇和島市 | うわじまアウトドアスポーツクラブ |
| 愛媛県 | 鬼北町 | 鬼北スポーツクラブ |
| 愛媛県 | 久万高原町 | 総合型久万スピリッツクラブ |
| 愛媛県 | 今治市 | なみかたジュニアスポーツクラブ |
| 愛媛県 | 今治市 | 総合型しまなみスポーツクラブ |
| 愛媛県 | 今治市 | NPO法人今治しまなみスポーツクラブ |
| 愛媛県 | 四国中央市 | 川之江TRACK&FIELDクラブ |
| 愛媛県 | 四国中央市 | UMAスポーツクラブ |
| 愛媛県 | 松山市 | ゆうポップスポーツクラブ |
| 愛媛県 | 松山市 | 総合型潮見地域スポーツクラブ |
| 愛媛県 | 松山市 | 愛媛大学総合型地域スポーツクラブ |
| 愛媛県 | 松山市 | 総合型地域スポーツクラブ春日館 |
| 愛媛県 | 松山市 | ONOスポーツクラブ |
| 愛媛県 | 松山市 | SCマツヤマ |
| 愛媛県 | 松山市 | アイススポーツクラブ |
| 愛媛県 | 松山市 | 久米総合型地域スポーツクラブ |
| 愛媛県 | 松山市 | ~かるスポ~石井村 |
| 愛媛県 | 松前市 | 北伊予ひまわりクラブ |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 金子地域文化スポーツクラブ |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 楽SPO船木 |
| 愛媛県 | 西予市 | 文化の里スポーツクラブ |
| 愛媛県 | 西予市 | のむらスポーツクラブ |
| 愛媛県 | 西予市 | みかめスポーツクラブ |
| 愛媛県 | 大洲市 | NPO法人おおずスポーツクラブ |
| 愛媛県 | 東温市 | NPO法人トレーフルスポーツクラブ |
| 愛媛県 | 東温市 | 川内さくらクラブ |
| 愛媛県 | 八幡浜市 | 楽スポGOやわたはまスポーツクラブ |
| 高知県 | いの町 | NPO法人いのスポーツクラブ |
| 高知県 | 安芸市 | 来楽部あっきぃーな |
| 高知県 | 越知町 | おちスポーツクラブ |
| 高知県 | 香南市 | NPO法人こうなんスポーツクラブ |
| 高知県 | 高知市 | ファミリークラブ江陽 |
| 高知県 | 高知市 | 一般社団法人高知チャレンジドクラブ |
| 高知県 | 高知市 | ぬのしだピカッとクラブ |
| 高知県 | 高知市 | はるのGENKIクラブ |
| 高知県 | 高知市 | 旭東スポーツクラブ |
| 高知県 | 佐川町 | NPO法人佐川町さくらスポーツクラブ |
| 高知県 | 四万十町 | NPO法人くぼかわスポーツクラブ |
| 高知県 | 四万十町 | 大正・十和スポーツクラブ |
| 高知県 | 室戸市 | NPO法人むろとスポーツクラブ |
| 高知県 | 宿毛市 | スポレクすくも |
| 高知県 | 仁淀川町 | 清流クラブ池川 |
| 高知県 | 仁淀川町 | さくらクラブ吾川 |
| 高知県 | 仁淀川町 | 仁淀スポーツクラブ |
| 高知県 | 須崎市 | NPO法人すさきスポーツクラブ |
| 高知県 | 大月町 | レッツおおつき |
| 高知県 | 中土佐町 | 鰹乃国スポーツクラブ |
| 高知県 | 土佐市 | NPO法人総合クラブとさ |
| 高知県 | 土佐清水市 | NPO法人スポーツクラブスクラム |
| 高知県 | 土佐町 | 土佐町Happinessスポーツクラブ |
| 高知県 | 梼原町 | 梼原雲の上スポーツクラブ |
| 高知県 | 南国市 | NPO法人まほろばクラブ南国 |
| 高知県 | 日高村 | ひだか茂平クラブ |
| 高知県 | 本山町 | もとやま元気クラブ |
| 福岡県 | みやこ町 | スポネットTOYOTSU |
| 福岡県 | 芦屋町 | NPO法人スポネット・しろやま |
| 福岡県 | 宇美町 | NPO法人ふみの里スポーツクラブ |
| 福岡県 | 苅田町 | 今古賀ふれあいスポーツクラブ |
| 福岡県 | 吉富町 | 吉富町体育協会 |
| 福岡県 | 久留米市 | NPO法人ウェブスポーツクラブ21西国分 |
| 福岡県 | 久留米市 | NPO法人田主丸カル・スポクラブ |
| 福岡県 | 久留米市 | 宮ノ陣笑群バイクラブ |
| 福岡県 | 久留米市 | 南薫クラブ |
| 福岡県 | 久留米市 | 筑西ゆめクラブ |
| 福岡県 | 久留米市 | 一般社団法人久留米市SC桜花台クラブ |
| 福岡県 | 久留米市 | 三潴体育振興協会 |
| 福岡県 | 宮若市 | 宮若いきいきスポーツクラブ |
| 福岡県 | 行橋市 | スポネットながお |
| 福岡県 | 香春町 | スポーツクラブかわら |
| 福岡県 | 糸島市 | 特定非営利活動法人ISC糸島スポーツクラブ |
| 福岡県 | 若松区 | NPO法人SFF若松サンシャインスポーツクラブ |
| 福岡県 | 宗像市 | 南の郷クラブ |
| 福岡県 | 春日市 | 特定非営利活動法人春日イーグルス |
| 福岡県 | 春日市 | NPO法人ふくようスポーツクラブ |
| 福岡県 | 小郡市 | 小郡わいわいクラブ |
| 福岡県 | 小倉南区 | 天神の丘スポーツクラブ |
| 福岡県 | 小倉南区 | NPO法人TOTOS北九州 |
| 福岡県 | 小倉北区 | NPO法人北九州陸上クラブRiC |
| 福岡県 | 上毛町 | こうげチャレンジクラブ |
| 福岡県 | 水巻町 | NPO法人水巻ゆう・あい倶楽部 |
| 福岡県 | 太宰府市 | 特定非営利活動法人太宰府よか倶楽部 |
| 福岡県 | 大川市 | NPO法人ペラーダ大川 |
| 福岡県 | 大野城市 | まどかスポーツクラブ |
| 福岡県 | 築上町 | NPO法人しいだコミュニティ倶楽部 |
| 福岡県 | 筑後市 | C.A.C筑後アクティブクラブ |
| 福岡県 | 筑後市 | 筑後アクティブクラブC.A.C |
| 福岡県 | 筑紫野市 | NPO法人カミーリア筑紫野スポーツクラブ |
| 福岡県 | 中間市 | なかま元気スポーツクラブ |
| 福岡県 | 中間市 | NPO法人colour |
| 福岡県 | 直方市 | わくわくクラブのおがた |
| 福岡県 | 直方市 | NPO法人GANDA |
| 福岡県 | 直方市 | Frech |
| 福岡県 | 東峰村 | らぶすぽ東峰 |
| 福岡県 | 那珂川市 | スポーツBRANDEX福岡 |
| 福岡県 | 那珂川市 | なかがわAC |
| 福岡県 | 八女市 | 一般社団法人SOUTHクラブ |
| 福岡県 | 八幡西区 | NPO法人香月・千代スポーツクラブ |
| 福岡県 | 八幡東区 | 特定非営利活動法人北九州スポーツクラブACE |
| 福岡県 | 飯塚市 | ボアソルテ・F・飯塚 |
| 福岡県 | 飯塚市 | 飯塚スポーツクラブ |
| 福岡県 | 飯塚市 | オリエントスポーツクラブ |
| 福岡県 | 福津市 | ふくつ総合型地域スポーツクラブドリームスポーツネットワーク |
| 福岡県 | 福津市 | 一般社団法人ルートプラス |
| 福岡県 | 豊前市 | ぶぜんピープルズ |
| 福岡県 | 豊前市 | 総合型地域スポーツクラブよろうや |
| 福岡県 | 門司区 | スポネット東郷 |
| 福岡県 | 柳川市 | 東宮永スポーツクラブ |
| 佐賀県 | 基山町 | スポーツ大国きのくに |
| 佐賀県 | 嬉野市 | 総合型うれしのほほんスポーツクラブ |
| 佐賀県 | 江北町 | がばい余暇クラブ |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 赤松スポーツクラブ・シャチ |
| 佐賀県 | 佐賀市 | NPO法人 かわそえスポーツクラブ |
| 佐賀県 | 佐賀市 | スポTOMO 東与賀 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | NPO法人 スポーツフォアオールサガユニックス |
| 佐賀県 | 鹿島市 | スポーツライフ・鹿島 |
| 佐賀県 | 上峰町 | 友遊スポーツかみみね |
| 佐賀県 | 多久市 | 多久スポーツピア |
| 佐賀県 | 太良町 | よかっ太良クラブ |
| 佐賀県 | 鳥栖市 | フィッ鳥栖 |
| 佐賀県 | 唐津市 | 玄海セーリングクラブ |
| 佐賀県 | 白石町 | ほっと有明クラブ |
| 佐賀県 | 武雄市 | さわやかクラブ武雄 |
| 佐賀県 | 有田町 | 有田スポーツクラブ“いきいき” |
| 佐賀県 | 有田町 | 西有田スポ・レク協会 |
| 長崎県 | 雲仙市 | 雲仙市がまだすスポーツクラブ |
| 長崎県 | 佐々町 | さざ倶楽部 |
| 長崎県 | 佐世保市 | 一般社団法人アイランズスポーツクラブ |
| 長崎県 | 佐世保市 | 相浦・日野総合スポーツクラブ |
| 長崎県 | 佐世保市 | NPO法人WillDo |
| 長崎県 | 佐世保市 | やまんた倶楽部 |
| 長崎県 | 佐世保市 | レゾナンスクラブ |
| 長崎県 | 佐世保市 | 東部スポーツクラブきずな |
| 長崎県 | 佐世保市 | スマイル江迎スポーツクラブ |
| 長崎県 | 佐世保市 | スポーツクラブなぎさ |
| 長崎県 | 時津町 | とぎつジョイクラブ |
| 長崎県 | 松浦市 | 今福町スポーツクラブふくふく |
| 長崎県 | 新上五島町 | 奈良尾スポーツクラブナッシーズ |
| 長崎県 | 川棚町 | 一般社団法人チューリップスポーツクラブ |
| 長崎県 | 大村市 | すずた総合スポーツクラブ |
| 長崎県 | 長崎市 | 西浦上スポーツクラブ |
| 長崎県 | 長崎市 | 東長崎総合型スポーツクラブ |
| 長崎県 | 長崎市 | 長崎市西部総合スポーツクラブ |
| 長崎県 | 長与町 | NPO法人総合型SC長与スポーツクラブ |
| 長崎県 | 東彼杵町 | スポーツクラブひがしそのぎ |
| 長崎県 | 南島原市 | NPO法人コミュニティースポーツクラブTEAMひまわり |
| 長崎県 | 波佐見町 | NPO法人法人ALH |
| 長崎県 | 平戸市 | 平戸総合スポーツクラブビクトリー |
| 長崎県 | 平戸市 | 一般社団法人総合型クラブたびスポ |
| 長崎県 | 諫早市 | スポコミいさはや |
| 大分県 | 宇佐市 | NPO法人総合型地域スポーツクラブ グレートサラマンダー |
| 大分県 | 宇佐市 | わっしょいUSAクラブ |
| 大分県 | 臼杵市 | 田野ふれあいクラブ |
| 大分県 | 臼杵市 | 下ノ江よろうちクラブ |
| 大分県 | 杵築市 | NPO法人OKYさわやかスポーツクラブ |
| 大分県 | 九重町 | ここのえ“夢”クラブ |
| 大分県 | 玖珠町 | 童里夢スポーツクラブ |
| 大分県 | 国東市 | NPO法人MAKK笑人クラブ |
| 大分県 | 佐伯市 | みなみスポーツクラブ |
| 大分県 | 佐伯市 | つるみ友クラブ |
| 大分県 | 佐伯市 | 本匠ホタッピィクラブ |
| 大分県 | 大分市 | NPO法人七瀬の里Nクラブ |
| 大分県 | 大分市 | ひしのみクラブ |
| 大分県 | 大分市 | NPO法人川添なのはなクラブ |
| 大分県 | 大分市 | NPO法人わいわい夢クラブ |
| 大分県 | 大分市 | NPO法人賀来衆倶楽部 |
| 大分県 | 大分市 | NPO法人おおみちふれあいクラブ |
| 大分県 | 大分市 | OZAI元気クラブ |
| 大分県 | 大分市 | みんなの明治クラブ |
| 大分県 | 大分市 | 明ゆうクラブ |
| 大分県 | 大分市 | 西の台あいあい倶楽部 |
| 大分県 | 大分市 | わさだ夢クラブ |
| 大分県 | 大分市 | 判田すこやか倶楽部 |
| 大分県 | 大分市 | NPO法人滝尾百穴クラブ |
| 大分県 | 大分市 | 総合型地域スポーツクラブ「佐賀関うみねこクラブ」 |
| 大分県 | 大分市 | 東稙田地域総合型地域スポーツクラブ「クローバークラブ」 |
| 大分県 | 竹田市 | 竹田スポーツ・レクリエーションクラブ |
| 大分県 | 中津市 | NPO法人洞門元気クラブ |
| 大分県 | 津久見市 | NPO法人エンジョイつくみ |
| 大分県 | 日出町 | 日出町総合型地域スポーツクラブ ひまわりのたね |
| 大分県 | 日田市 | あまがせスポーツクラブ |
| 大分県 | 姫島村 | 姫島ふれあいスポーツクラブ |
| 大分県 | 別府市 | にこしんクラブ |
| 大分県 | 別府市 | あさみ川クラブ |
| 大分県 | 別府市 | ほくぶスポーツクラブ |
| 大分県 | 別府市 | 南立エンジョイ倶楽部 |
| 大分県 | 別府市 | 大平山湯の街クラブ |
| 大分県 | 豊後高田市 | NPO法人TMKチャレンジクラブ |
| 大分県 | 豊後大野市 | みえスポーツクラブ |
| 大分県 | 豊後大野市 | おがたいきいきスポーツクラブNest |
| 大分県 | 豊後大野市 | NPO法人朝地フレンドクラブ |
| 大分県 | 由布市 | NPO法人ゆふいんチャレンジクラブ |
| 大分県 | 由布市 | みことスマイルインクラブ |
| 大分県 | 由布市 | スポーツクラブHASAMA |
| 宮崎県 | えびの市 | NPO法人真幸ホットほっとクラブ |
| 宮崎県 | えびの市 | NPO法人いいの夢クラブ |
| 宮崎県 | えびの市 | NPO法人いい汗加久藤クラブ |
| 宮崎県 | 延岡市 | 南方ワイワイスポーツクラブ |
| 宮崎県 | 宮崎市 | NPO法人 東大宮スポーツクラブ |
| 宮崎県 | 宮崎市 | みやざき中央スポーツクラブ |
| 宮崎県 | 宮崎市 | NPO法人佐土原スポーツクラブ |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 住吉スポーツクラブ |
| 宮崎県 | 宮崎市 | NPO法人MIYAZAKIうづらaiクラブ |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 半九レインボ-SC |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 青島スポーツクラブ |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 木の花スポーツクラブ |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 潮見スポーツクラブ |
| 宮崎県 | 宮崎市 | NPO法人FC roby |
| 宮崎県 | 串間市 | 一般社団法人串間スポーツクラブ |
| 宮崎県 | 高原町 | 神武くんスポーツクラブ“きらり” |
| 宮崎県 | 高鍋町 | 特定非営利活動法人 高鍋スポーツクラブ |
| 宮崎県 | 三股町 | NPO法人みまたチャレンジ総合クラブ |
| 宮崎県 | 小林市 | 小林元気クラブ |
| 宮崎県 | 小林市 | クラブのじり |
| 宮崎県 | 西都市 | 西都スポーツクラブ |
| 宮崎県 | 西米良村 | メラスポチャレンジクラブ |
| 宮崎県 | 川南町 | 川南スポーツ合衆国 |
| 宮崎県 | 都城市 | NPO法人都城ぼんちスポーツクラブ |
| 宮崎県 | 都城市 | 一般社団法人 とみさか |
| 宮崎県 | 都城市 | NPO法人都城スポーツクラブシエロ |
| 宮崎県 | 都農町 | NPO法人都農enjoyスポーツクラブ |
| 宮崎県 | 日向市 | ひむかYOUゆうクラブ |
| 宮崎県 | 日南市 | 一般社団法人日南市スポーツクラブ |
| 宮崎県 | 日之影町 | ひのかげきらめきクラブ |
| 宮崎県 | 木城町 | 木城ドリームス |
| 熊本県 | あさぎり町 | ふれあいスポーツクラブあさぎり |
| 熊本県 | 阿蘇市 | NPO法人火の山スポーツクラブ |
| 熊本県 | 宇城市 | NPO法人不知火クラブ |
| 熊本県 | 宇城市 | UKIおがわクラブ |
| 熊本県 | 宇城市 | NPO法人総合型クラブSCC宇城 |
| 熊本県 | 宇土市 | NPO法人うとスポーツクラブ |
| 熊本県 | 嘉島町 | 嘉島町総合型地域クラブ |
| 熊本県 | 菊陽町 | NPO法人クラブきくよう |
| 熊本県 | 玉東町 | オレンジはあとクラブ |
| 熊本県 | 玉名市 | いだてん玉名 |
| 熊本県 | 熊本市 | 日吉地域総合型スポーツクラブ |
| 熊本県 | 熊本市 | NPO法人桜木ふれあいスポーツクラブ |
| 熊本県 | 熊本市 | ほくぶ総合スポーツクラブ |
| 熊本県 | 熊本市 | 龍田地域なかよしスポーツクラブ |
| 熊本県 | 熊本市 | 長嶺地域スポーツクラブ |
| 熊本県 | 熊本市 | 花園スポーツクラブ |
| 熊本県 | 熊本市 | 東部地域総合型スポーツクラブ |
| 熊本県 | 熊本市 | NPO法人スポレク・エイト |
| 熊本県 | 熊本市 | 天明総合スポーツクラブ |
| 熊本県 | 熊本市 | 城北スポーツクラブ |
| 熊本県 | 熊本市 | 帯山地域スポーツクラブ |
| 熊本県 | 熊本市 | エス・エス・月出 |
| 熊本県 | 熊本市 | 御幸スポーツクラブ |
| 熊本県 | 熊本市 | NPO法人u&uNスポ植木 |
| 熊本県 | 熊本市 | あきた総合型スポーツクラブ |
| 熊本県 | 熊本市 | 託麻西校区総合型スポーツクラブ |
| 熊本県 | 熊本市 | くまもと城南スポーツクラブ |
| 熊本県 | 熊本市 | 田迎地域スポーツクラブ |
| 熊本県 | 熊本市 | 火の君スポーツクラブ |
| 熊本県 | 熊本市 | NPO法人とみあい総合型クラブ |
| 熊本県 | 御船町 | フネッピーすこやかスポーツクラブ |
| 熊本県 | 甲佐町 | I・YOUスポーツ&カルチャークラブ |
| 熊本県 | 荒尾市 | 中央ふれあいスポーツクラブ |
| 熊本県 | 高森町 | 高SPO |
| 熊本県 | 合志市 | クラブこうし |
| 熊本県 | 合志市 | ヴィーブル FUN クラブ |
| 熊本県 | 山鹿市 | やまが総合スポーツクラブ |
| 熊本県 | 産山村 | 産山ヒゴタイ・スポーツクラブ |
| 熊本県 | 小国町 | 小国ゆうあい倶楽部 |
| 熊本県 | 上天草市 | NPO法人上天草スポーツクラブドリームズ |
| 熊本県 | 上天草市 | アロマクラブ |
| 熊本県 | 人吉市 | カルヴァーリョ・ラッソ人吉 |
| 熊本県 | 水俣市 | サンビレッジみなまたスポーツクラブ |
| 熊本県 | 水俣市 | NPO法人ヴィラノーバ水俣 |
| 熊本県 | 大津町 | NPO法人クラブおおづ |
| 熊本県 | 長洲町 | NPO法人長洲にこにこクラブ |
| 熊本県 | 津奈木町 | つなぎ運動します隊 |
| 熊本県 | 天草市 | うしぶかイキイキクラブ |
| 熊本県 | 湯前町 | 湯前さわやかクラブだんだん |
| 熊本県 | 南阿蘇村 | クラブ南阿蘇 |
| 熊本県 | 南関町 | NPO法人A-lifeなんかん |
| 熊本県 | 八代市 | さかもと未来クラブ |
| 熊本県 | 八代市 | DREAM火流 |
| 熊本県 | 八代市 | やつしろ総合型クラブ「リ・ボンズ」 |
| 熊本県 | 美里町 | 元気・夢クラブ |
| 熊本県 | 氷川町 | ひかわスポーツクラブ |
| 熊本県 | 苓北町 | クラブれいほく |
| 熊本県 | 和水町 | クラブなごみ |
| 鹿児島県 | 姶良市 | NPO法人姶良スポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 伊佐市 | 大口健康スポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 屋久島町 | やくしま仲良しコミスポクラブ |
| 鹿児島県 | 喜界町 | きかい100スポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 薩摩川内市 | NPO法人川内スポーツクラブ01 |
| 鹿児島県 | 薩摩川内市 | ひわきYOU遊スポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 指宿市 | NPO法人いぶすきスポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 | NPO法人NIFSスポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 | NPO法人かのや健康・スポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | NPO法人SCC |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | めいざんスポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 花野スポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 郡山スポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 中郡校区地域スポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | ソンタスポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 桜島スポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 吉野台地スポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | NPO法人SEED |
| 鹿児島県 | 出水市 | NPO法人フェリシドスポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 出水市 | いずみわくわく夢クラブ |
| 鹿児島県 | 西之表市 | 種子島スポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 曽於市 | コミュニテイスポーツクラブそお文化村 |
| 鹿児島県 | 南さつま市 | 南さつまコミュニティスポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 日置市 | コミュティスポーツクラブチェスト伊集院 |
| 鹿児島県 | 霧島市 | NPO法人隼人錦江スポーツクラブ |
| 鹿児島県 | 与論町 | NPO法人ヨロンSC |
| 鹿児島県 | 和泊町 | 元気!わどまりクラブ |
| 沖縄県 | 恩納村 | 一般社団法人はまゆうスポーツクラブ |
| 沖縄県 | 糸満市 | NPO法人沖縄健康づくり協会ダブルピース |
| 沖縄県 | 石垣市 | 一般社団法人石垣島アスリートクラブ |
| 沖縄県 | 南城市 | 総合型クラブTEAMたまぐすく |
| 沖縄県 | 南城市 | さしきスポーツクラブ |